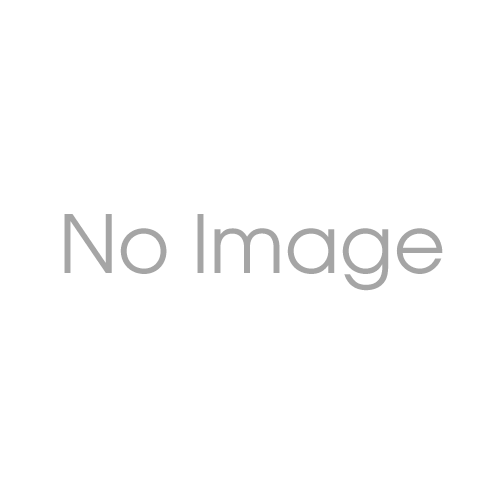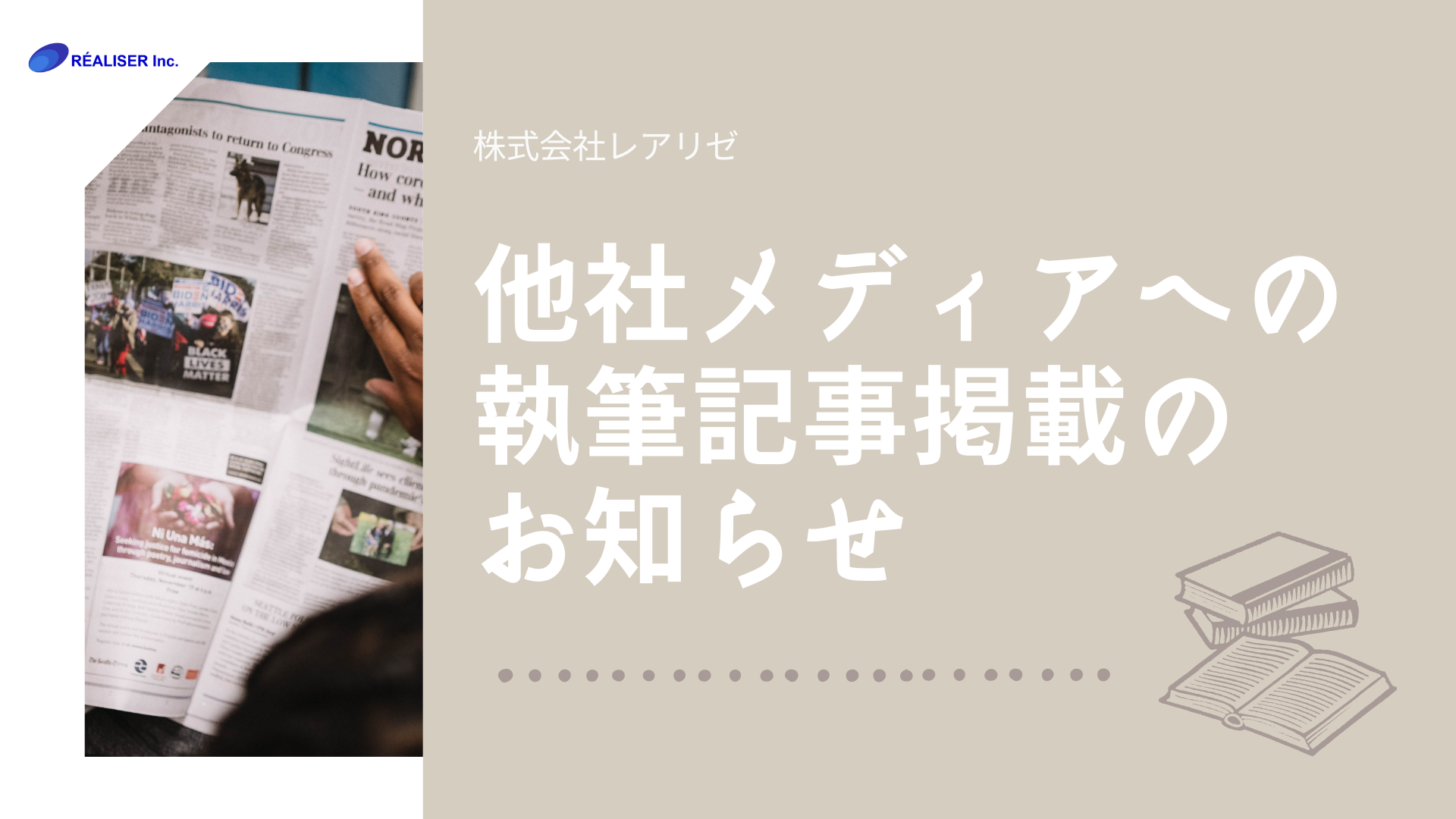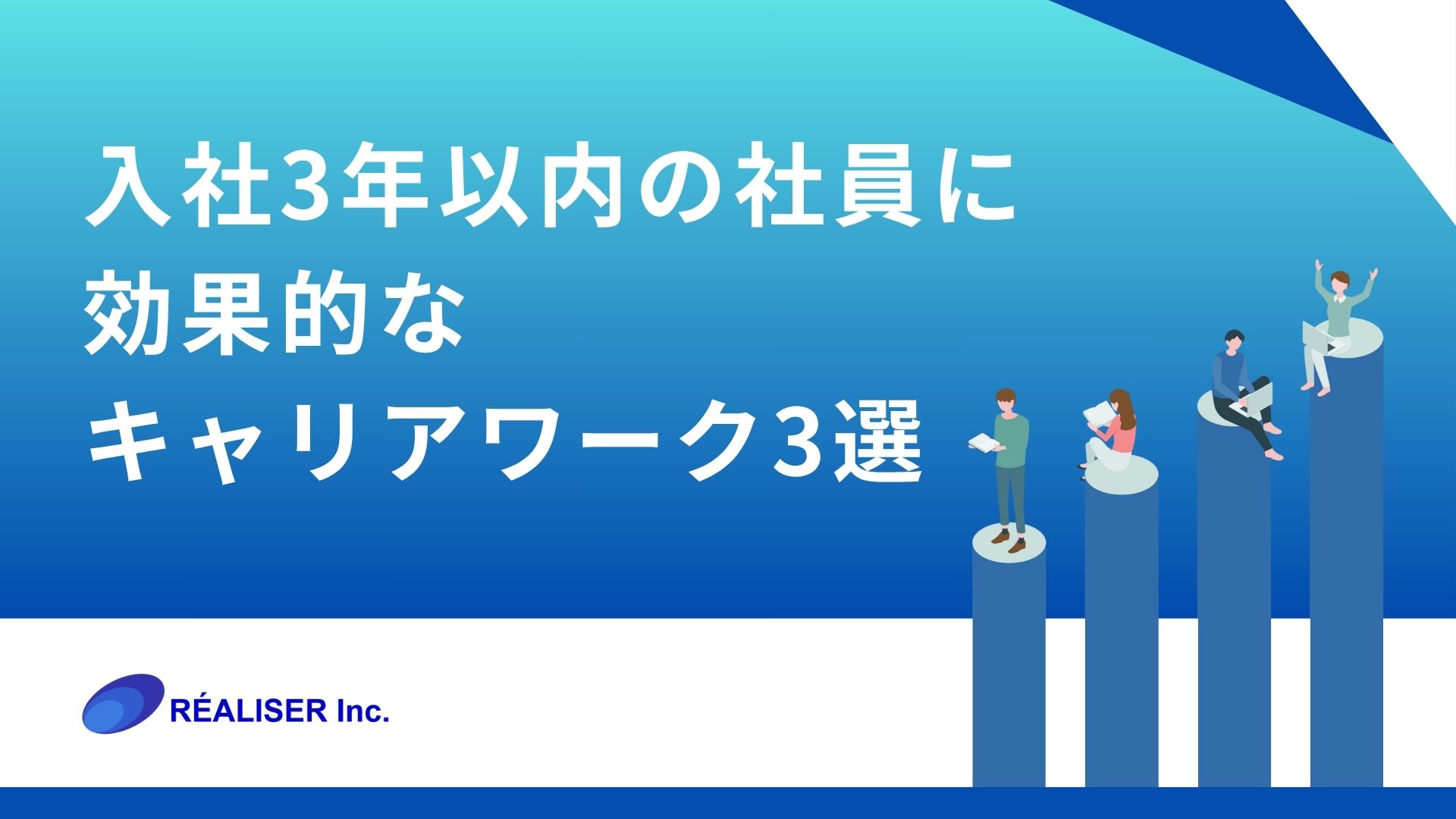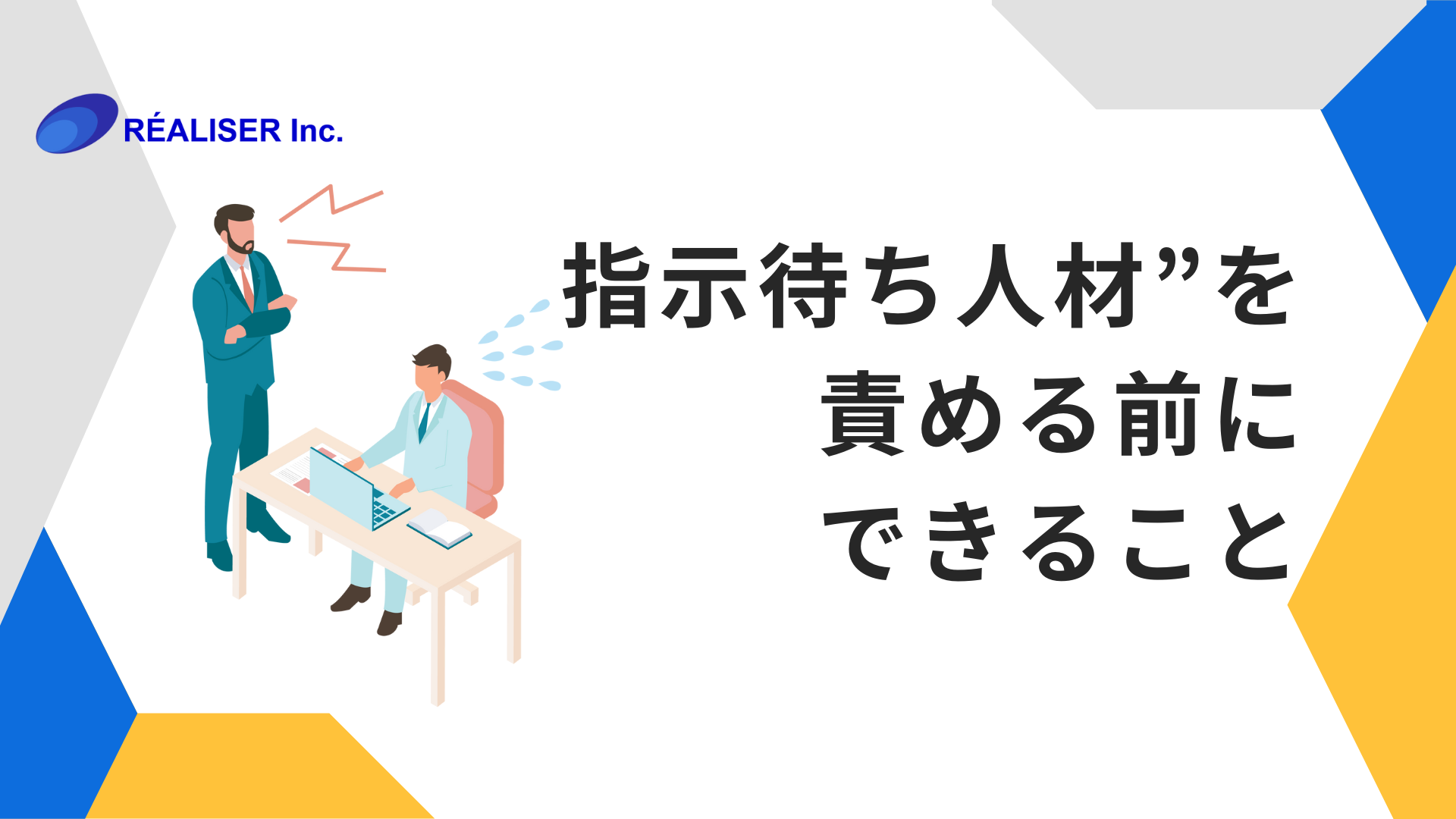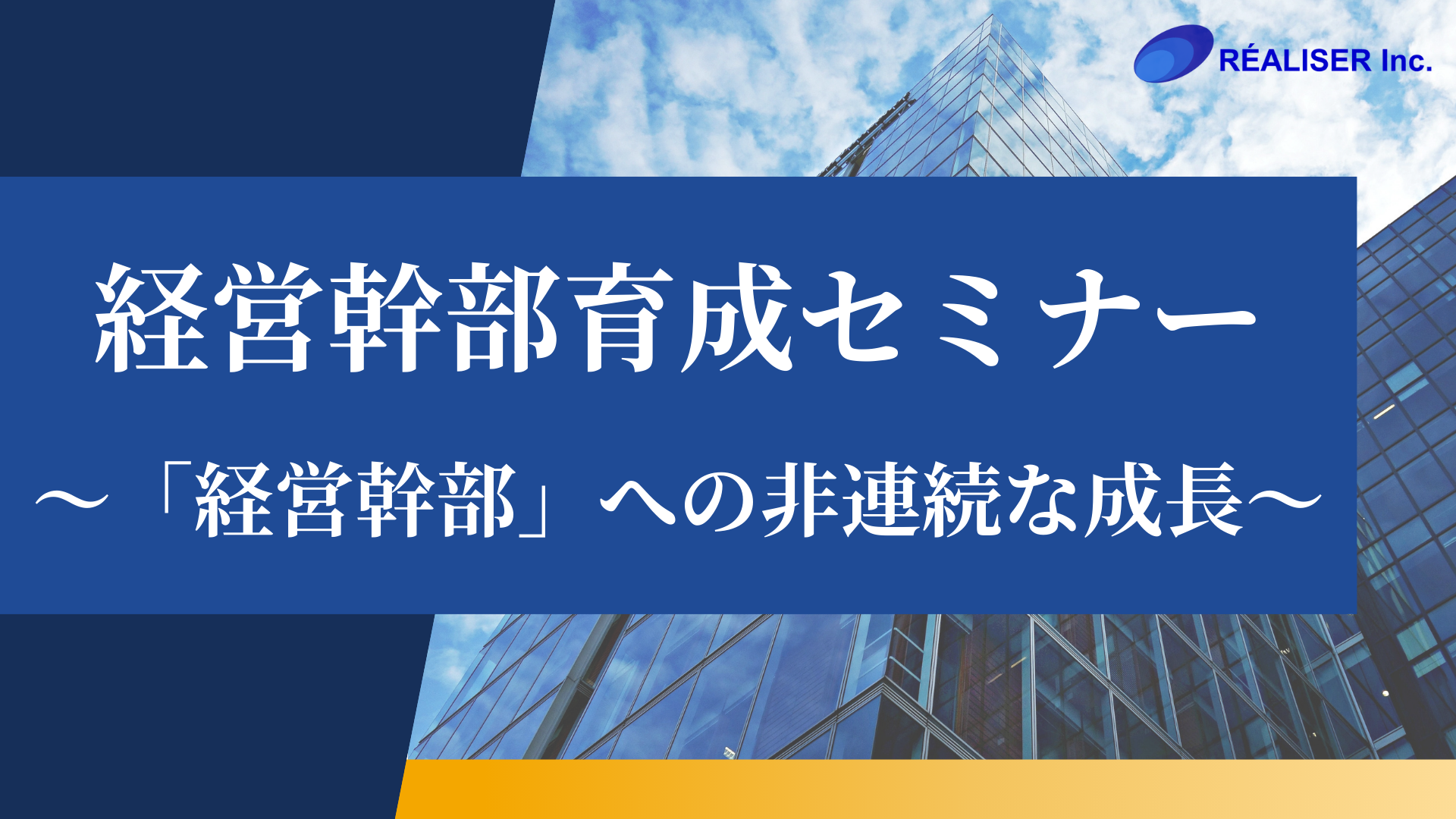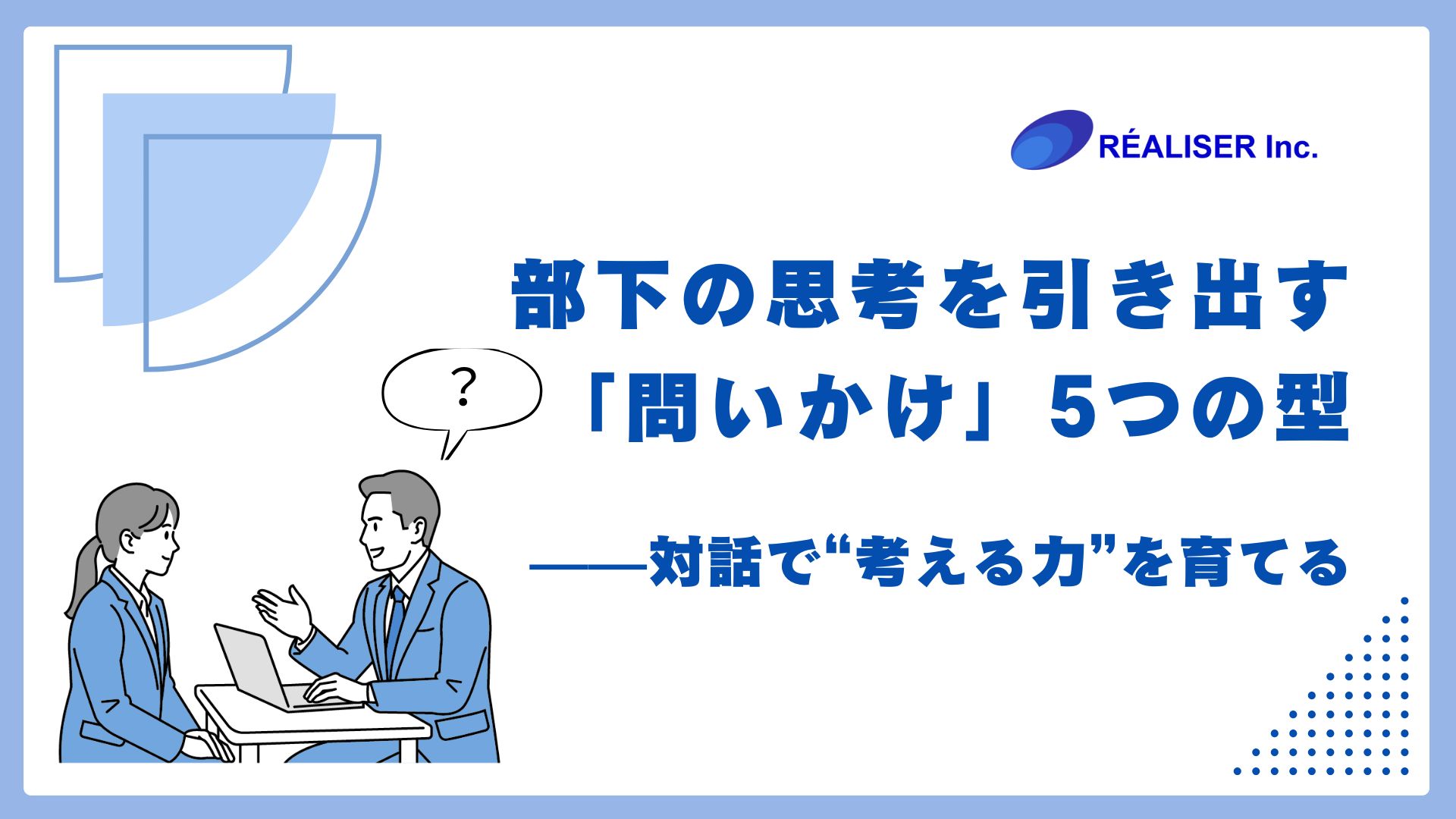
部下の思考を引き出す「問いかけ」5つの型——対話で“考える力”を育てる
1.はじめに:問いが変われば、関係が変わる
部下の主体性を育てたい——そう願いながらも、現場では「自分で考えてくれない」「受け身で反応が薄い」と感じている管理職も少なくありません。
しかし、よくよく見てみると、部下が“考えていない”のではなく、“考えるきっかけを与えられていない”というケースも多く存在します。
実は、日々の1on1や面談での「問いかけ」ひとつで、部下の思考スイッチは大きく変わります。問いは、上司が与える“情報”ではなく、部下の内側に眠る“仮説”や“気づき”を引き出すトリガーなのです。
この記事では、1on1や日常の対話にすぐ活かせる「問いかけの型」を5つに分けてご紹介します。目的に応じた問い方を知ることで、より実践的に「考える力を育てる関わり方」が見えてきます。
2.【内省型】「自分の経験から学ばせる」問い
■目的:体験の振り返りから学習を促す
- 「今回の仕事で印象に残っていることは?」
- 「うまくいった理由は何だったと思う?」
- 「もしやり直せるとしたら、何を変える?」
このタイプの問いは、行動→振り返り→教訓化という“学習と成長のサイクル”を回すために有効です。
特に、同じ失敗を繰り返しやすい部下には、外から指摘するのではなく、内省を通じて“自分で気づかせる”アプローチが効果的です。
たとえばある企業では、プロジェクト終了後に必ず「個人振り返りシート」を記入させ、その内容を1on1で共有するようにしています。
そこには、「一番手ごたえを感じた瞬間」「もっと工夫できた場面」「チームに貢献できたこと」など、具体的な問いが並んでいます。
こうした内省の定着は、次の挑戦を前向きに捉える習慣づくりにもつながります。
3.【視点変換型】「他者や目的に目を向けさせる」問い
■目的:一人称の視点に偏った思考を広げる
- 「相手はどう受け取ったと思う?」
- 「チーム全体から見ると、どうだった?」
- 「この仕事の本来の目的は何だった?」
視野が狭くなっているときは、「目的」「相手」「全体」といった軸での問いかけが有効です。ときには図を使って関係性を整理したり、言語化できない気づきに寄り添う姿勢も重要です。
たとえば、ある営業担当の社員が顧客向けの提案に悩んでいたとき、「自分の売りたいサービスをどう伝えるか」ばかりを考えていました。
そこで上司が、「今回のお客様は何を一番大切にしてると思う?」と投げかけたところ、「コストより導入後のサポート体制に不安があるって言ってたかもしれません」と、相手の視点に立った発想が生まれました。
このやり取りをきっかけに、提案内容も“自社の強み”ではなく、“相手の期待や課題”を起点に組み立て直され、商談の手応えも大きく変わったそうです。
視点を変える問いは、考える方向そのものをリフレーミングする力があります。
4.【展開型】「選択肢を広げる」問い
■目的:一つの考えに固執せず、柔軟な思考を促す
- 「他にどんな方法が考えられる?」
- 「もう1案出すとしたら?」
- 「逆の立場だったら、どう対応する?」
「正解探し」や「上司の意図読み」に偏りがちな部下には、あえて複数案を出す問いが有効です。
アイデアは数を出すことで質が上がるため、“考える体力”を育てる意味でも定期的に取り入れたい型です。
特に企画職やマーケティング系の職種では、「これがベスト」という思考に陥ると、柔軟な発想が止まってしまいます。
「ちょっと突飛でもいいから、あと2案考えてみて」という問いで、思考のブレーキを外すことができます。
5.【決断支援型】「選び、決める」問い
■ 目的:自己決定と責任意識を引き出す
- 「いくつかある中で、どれが最も効果的だと思う?」
- 「この案で行くと決めた理由は?」
- 「やるとしたら、どこから始める?」
「考える」だけでなく、「決める」ことで思考は深まります。自分で判断したことには責任も生まれやすく、次の行動への納得感も高まります。問いは選択と実行のサイクルを回す起点になります。
これは特に中堅社員の育成に効果的です。
たとえば、「A案とB案、どちらも良さそう」と迷っている社員に対し、「あなたが責任を持って選ぶとしたらどちら?」と尋ねるだけで、表情が変わることがあります。
選択の機会を与えられていない人は、そもそも“決める癖”が育っていないのです。
6.【関係性深化型】「対話の土壌を耕す」問い
■ 目的:信頼・安心感を育む
- 「最近、気になっていることある?」
- 「話しておきたいこと、何かある?」
- 「やってみて、どうだった?」
関係性ができていない状態での問いかけは、建前や表面的な答えになりがちです。
まずは「話してもいい」「受け止めてもらえる」という感覚を育てることが、“本音の対話”の前提になります。
この型の問いは、1on1の冒頭や雑談タイミングに取り入れるのが効果的です。
「調子どう?」のような曖昧な問いよりも、「最近、気になっていることがあったら教えてね」など、明確で柔らかい問いの方が話しやすさを引き出します。
また、ちょっとしたメモやリアクションに対して、「それ、面白いと思ったけど、もう少し聞かせて」と深掘ることも、安心感につながります。
信頼の積み重ねは、次の実務的な問いかけの“通り道”にもなります。
7.おわりに:問いかけは「支援」
問いとは、相手の内面と向き合う行為です。
相手を変えるためのコントロールではなく、自ら考える力を引き出す“支援”のひとつ。だからこそ、問いかけには誠実さと信頼が問われます。
問い方を変えることで、部下の反応が変わる。それを実感したとき、1on1や日常の会話が単なる業務確認の場ではなく、“育成の場”へと変わっていきます。
まずは、5つの型のうちどれかひとつだけでも、明日の1on1で使ってみてください。そして、その答えに耳を傾ける時間こそが、部下の思考を耕す最良の機会になるはずです。
対話の質は、問いの質。問いの質は、関係性の質です。問いを磨くことは、部下との信頼関係を育て、組織の未来をつくる第一歩になるかもしれません。

レアリゼのオーダーメイド研修
組織や受講生の課題に合わせて、より効果的な研修をおつくり致します。 「こんな研修をしたい」「○○を社員に理解してほしい」といったご相談など、お気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちら