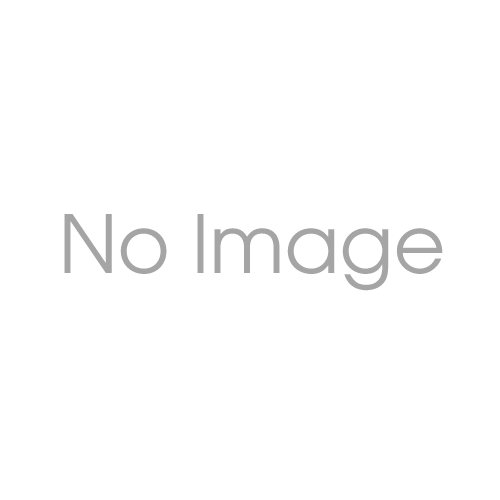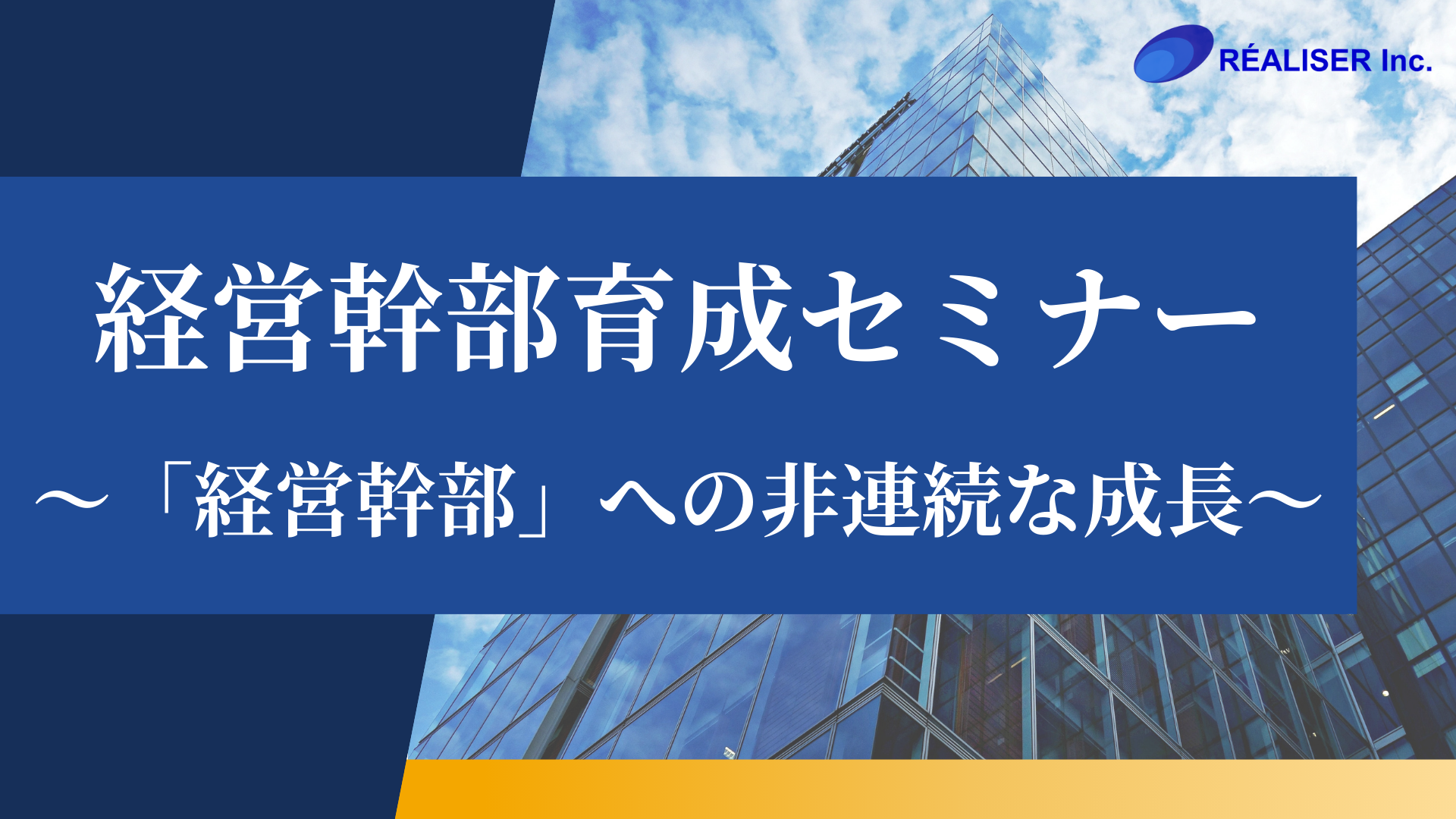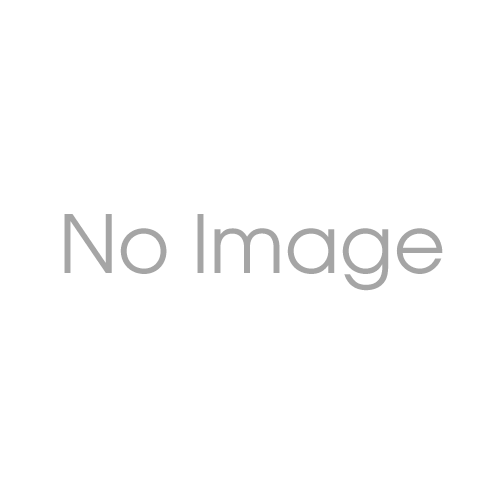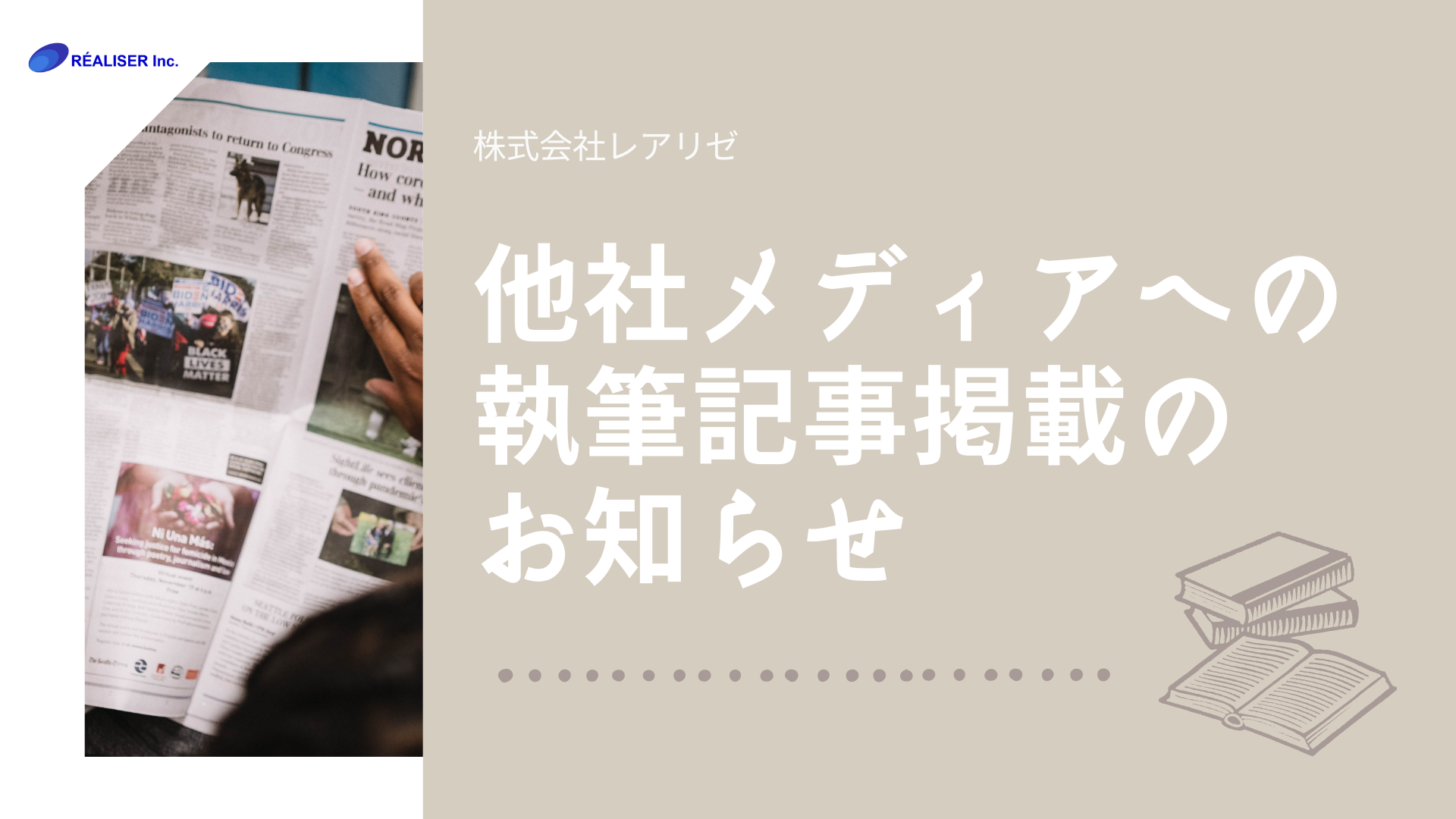L.E.T. (Leader Effectiveness Training)の専門家
辻 達諭(つじ たつや)氏と弊社真田との対談
対談者様情報

辻 達諭(つじ たつや)氏
株式会社ヒューマンスキル開発センター 協力講師
L&Cトレーニング株式会社 代表取締役
教授システム修士/SL(状況対応リーダーシップ)指導員/Disc認定インストラクター、TA(交流分析)インストラクター/LET認定トレーナー/アクションラーニング認定コーチ/ハーマンモデル認定講師
職歴
1986年~1996年(社)日本能率協会
1996年~2000年(㈱)日本能率協会マネジメントセンター
2000年~2005年 ソニー・ヒューマンキャピタル㈱
2001年~2005年 ソニー㈱人材開発部
2005年~2015年 ソニーセミコンダクタ㈱
2015年~ L&Cトレーニング㈱設立
ヒューマンスキル開発センター協力講師
※部署・役職はインタビュー当時のものです
L.E.T. (Leader Effectiveness Training)の専門家 辻 達諭氏と弊社真田との対談
真田:辻さんは「L.E.T. (Leader Effectiveness Training)」の専門家でいらっしゃいますが、まずご自身のご経歴やL.E.T.の専門家になられたきっかけをお話いただけますか?
辻:学校は工学部の土木学科出身で元々理系なのですが、ご縁があり広告制作会社に入社しました。
工作機械の企業のパンフレットを作る時に、技術を理解していないと書けないということでご縁があり、お声掛けをしていただきました。
技術者の方々はとても真面目で「このような問題があります」ということを具体的に教えてくれますから、それをどのように文章で表現するかということに悩み、いろいろな先輩に相談していると、私はおそらく編集系のほうが合っているのでは?ということになり、スポーツ系の雑誌社で働きました。そこでいわゆるマリンスポーツ、(ヨットやモーターボート)の雑誌の編集に携わり副編集長までやらせて頂きました。
そこで出会ったヨットのオーナーの人たちが経営者の方々ばかりで、その時に「会社」というものが一体どういうものなのか、ということを経営者の方を通して教えて頂きました。
それまではいわゆる一技術しか知らなかった私は「もっと会社経営のことを学びたい」と思いはじめ、それなら会社経営も学べる「日本能率協会という会社があるよ」という話を聞き、自分の勉強にもなるので、日本能率協会に入ったっていうのが経緯です。
私が入社し、ネットを使ったビジネスを立ち上げていこうと考え、能率協会のEラーニングを作っていました。
日本能率協会で事業の立ち上げを行っていると、たまたまSONYの人事センター長だった日本能率協会の評議員の方が、私のことを「変なのがいるなぁ」と思っていたらしく、
SONYでもネットビジネスを立ち上げていく状況だったので「ではうちに来ませんか?」と、お声がけをいただきました。
SONYに興味はありましたが、日本能率協会で事業を立ち上げて頑張っていこうと思っていたので断りに行ったんですが、色々な視点が視点が持てるチャンスがあると思い、それでSONYに入社しました。
SONYに入社し、僕が就いた上司が優秀な方で、かなり権限を使うタイプの人でした。
「すごい業績を上げてきた優秀な人なのに、なぜ部下がついていかないんだろう?」「なぜみんな倒れてしまうんだろう?」と、本人に原因があるのか?本人の一体何が原因なんだろうか?もちろん性格なども要因のひとつではありますが、おそらく振る舞いが原因なのではないかと考えました。
一度それをつぶさに整理しようと、それがおそらく今につながる最初のトリガーだったと思います。
当時僕が自分のスキルとして一番使っていたのは、ID、インストラクショナル・デザインで、今で言う"インストラクショナル・システム・デザイン"です。
あれは日本能率協会の時に、eラーニングやプランを作るという時に、IDの考え方はとても重要でした。講師の勘と経験で作るプログラムではなく、きっちり作りたかったんです。そういったことがあったので、そのID的な観点で後輩の課題、スキルを分析してオブジェクティブの設定などをやっている中に、やっぱり人の要素って大きいなと考えるようになりました。事実そう思います。優秀な人を集めていますし、集まりますから。
「優秀なのになぜ成果が出ない?」というほんとによくあるテーマみたいなことが課題に挙がり、当時のイメージとしては、ブラックボックスなんです。
今はだいぶ浸透してきている"サーバントリーダーシップ"の考え方もあるし、他のいろんな欲求理論ももうちょっと違う形で出てきました。コーチングというのもその後にでてきました。
真田:SONYではかなりコーチングも実施されていましたよね?
辻:そうですね。やっても全然成果が上がらないというケースが多かったです。実際に「それコーチングなの?」というものも多かったです。
そういう中で、いろんなプログラムを見てもうひとつ勉強になったことは、イブカさん、モリタさん、オオガさんのビデオでした。
私は、時間があったのでほとんど見たんですが、言葉は違えども何を言わんとするのかというところは、やっぱり見えてきます。
イブカさんは技術も語るし美術も語ります。ですが「人としてどうあってほしいか」ということがやはり背景に強くあるように感じました。
直接そう語られる部分もあるんですけど、正確な言葉ではないかもしれないけど、「人間主義に基づいて」と書いていました。真面目な技術者の能力を最大に生かすのに「人間主義に基づいて」と書いてあるんです。
ひょっとするとそれは、戦前の軍国主義的な、人を人とも思わぬそういう風潮とか、そういったものが背景にあったのか、当たり前すぎてそこに光を当てなかったのかもしれないけれど、でも意外に会社って人間主義というところで見ると、何となくそこから離れてしまってる時間があるように感じたんです。
ですが「人間主義」というところがないと、結局成果上がらないっていうことになります。
それでひとつ思ったのは、部下である時にはいろんな上司の人がいて、この人についていこうと思える人もいれば、とてもこの人の下にはついていけないと思える経験はみなさんしていると思います。質も違うし量も違うし、場面も違うけども、フラットで見るとそうだと思います。モリタさんもそう話されていました。
多くのマネージャーは良かれと思ってやっていますが、部下が自分をどう思うかとか、そういうところに関しては人間主義というよりは業績とか技術とか、そういったところに注視しています。
何か少し違うバランスになってしまったのかなと。もちろんサラリーマンですから好き嫌いで仕事をしてはならないとか、そういう良識がある前提の話なのですが、それでも人間の心や想いは、やはりこの人にはついていけないと思ったらパフォーマンスは落ちると思います。それでも上げなきゃいけないと思うのは責任感なのかもしれません。
だから自分自身の技術やお客さんなど、別のところにモチベーションを求めるのかもしれません。
ですが、一番身近な上司・部下、あるいは同僚との人間関係がモチベーションに影響を与えているとしたらやはりそこはカギになると思います。実際、私もそういう体験をたくさんしてきました。そして部下が抱えている教育の課題についても、分析してみるとどうもそこがカギでした。
そういうところから、何かプログラムがないか、良いものはないかいろいろ当たり始めその中のひとつで関心を持ったのが、真田さんが取り組まれていたサーバントリーダーシップにつながる、モチベーションに関して光を当てたプログラムでした。
真田:そもそも、何で知ってたんですか?
辻:具体的なトリガーはちょっとわからないんだけど…
真田:もう大昔ですから。
辻:ただ、僕の後輩と話すると、僕に連れていかれて真田さんのところに行った、という人が多いんですよ。真田さんの話を聞きに行ったと。多分ホームページとか、ちょうど会社を立ち上げて…数年ぐらいですかね?
真田:その時はヒューマンキャピタルのお立場でしたっけ?
辻:その時はね、PPO…ヒューマンキャピタルにはいたんだけど、人事の中の人材育成にいたタイミングかもしれないです。
真田:ヒューマンキャピタルからSONYの人事にまた移って?
辻:まあ両方育成系やったんですよ。兼任していました。
真田:L.E.T.もそのタイミングですか?
辻:L.E.T.は、実は存在はもっと前からしてたんです。親業をしていて、20代の時に。
それはたまたま僕のおじさんが親業のインストラクターをしていました。
おじさんがやってることだからあまり評価をしていなかったんですが、でも親業の内容になるとちょっと…と思いました。親業の内容を会社で行う事も考えましたが、やっぱり拒否反応が強く、中身をわかってしまうと同じだねとは言えるんですけど、でもやはり、特にエンジニアだと…L.E.T.と親業の違いで言うと、親業はやはり子供が相手なのでやや感情的なものを重きにします。
問題解決って言っても子供には限界がありますので、例えば環境を整えてあげるとか…そういう支援というよりは援助的な要素が入ってくるんですよ。しかも出てくる事例も「〇〇ちゃん大変だね」みたいに。エンジニアには、そういうのは違うと思いました。
それとは別に、モリタさんがビデオの中でもう一つお話をしていたのが、やはりみんながコンビンスして、納得してもらいモチベーションを高めていくような、そういう人のマネジメントの技術が必要だと。アメリカにはありますが、日本にはないとビデオで言っています。
では、アメリカにどんな技術があるかという事で、モリタさんの来歴とか周辺の話とか聞いてみていくと、実はキッシンジャーさんと仲が良いことがわかり、キッシンジャーの外交の補佐をやってたのがトーマス・ゴードンだったんです。
具体的には、カーター大統領の外交の顧問をやってたんです。なので、交渉とかコミュニケーション、つまり対立を解決するという観点でしょう。第1回中東和平はカーターの業績でありますけども、少なくとも和平合意を作れたという事は、トーマス・ゴードンの…
その辺で、「あれ?ひょっとして」と思い、L.E.T.の本をもう1度読み直しました。特に、なぜリーダーはコミュニケーションスキルが必要だとかを読んでみると、コンビンスとか、モリタさんが使ってた単語がたくさん出てきました。
L.E.T.をやっていると、その組織の業績はどうですか?とよく聞かれます。「業績は良いです」と答えますが、なかなかピンとこないんです。それで良いと思っていますけど、逆にL.E.T.をやってるけれど業績が悪いとしたらそれはプログラムに問題があると。
真田:でも業績というのは、いろんな複合要因じゃないですか。
ちょっと乱暴だと思いますけど、効果がない研修を実施していても業績が良いこともありますよね?マーケットが良ければ。
辻:そうですね。それでひとつ思ったのは、その反語じゃないけれど、L.E.T.をやっていて業績が悪いとしたら、そのプログラムに問題があるというのは、結局良い時はいろんな要素で良くなるんだけど、悪い時は他の要素で悪くなるんだけど、そこをカバーできるはずだという発想がどうもあるみたいです。
例えば厳しい時とかは、業績も当然波打ちますし、その環境要因も大きいわけです。リーマンショックがあればみんな悪いわけですから、その時に人間関係の質も整ってなくてコミュニケーションの質も悪くて、業績悪いから何が悪いかって、相当悪くなります。
真田:最初は業績ですけども、でも元々の問題意識の中で業績の立て直しに行かれたというよりは、離職の問題や労務問題の課題があったわけですね。そういった意味での変化というのはどうなんでしょう。
辻:労務問題はゼロではないですけども減ったと思います。本当に重篤なのは減ったと思いますね。
ゼロではないですけれど、時々重篤なのが起きるのは本社から大勢来た時に起きました。本社からあるタイミングで大勢来たら、やはりそういう問題が起きたので、人間関係の質を高めるアプローチを学んでる人たちと全く学んでない人たちの間では、やはり差があるのだと思いました。
今もあるんですが、少し上から物を言うとか、暴力まではいかないですが、かなり厳しいパワハラみたいな事があります。それこそ労務問題になるまでいかずに終わってるっていうのは、やはり何かみんな学び取ってるのかもしれません。
言われる方も学んでますし、やっている方も学んでるから、どこかで前向きになってるところがあるんではないでしょうか。そういう風にやってる時というのは、そのチームの業績が悪い時なんですね。まあ普通に考えてもそうですよ。
業績良かったら、あんまりガミガミ言わなくていいけど、悪いからガミガミ言うようになるんです。それで、今僕は最初にそうやって言われた時に、ボトムラインとその一連のリーダーシップ教育が、それでいいじゃないかって言われるのがピンとこなかったのが、今ではそれでもいいのかなって思ってるのはそれが理由です。
真田:もうひとつの観点で、高度な技術的なことをやるという意味で、技術的な成功というか開発の進捗とか、そういう意味ではどうだったんでしょうか?
辻:ボトムラインを支えてるんですけども。これは僕が勝手に、我田引水的に証言してしまうんだと思いますが、成果を上げているチームはたった一人の優秀な技術者だけで何か技術を確立してるわけではありません。少ない人数ではあるけどそれを生産するというところに能力があるわけですよ。いろんな専門家集団が集まり動かなくてはならないということは、その中での人間関係の築き方とか、話題のほとんどは技術的なことかもしれませんが、その人のつながりが上手くいったから成果を出せたのではないかと思ってます。
それで最近になってある大手企業の方に言われたのが、コミュニケーションの質が製品の質を左右する時代になってきたと。
昔はある技術だけで製品を作って成果を上げられたのが、いろんな技術を集めて成果を出さないといけません。価値観も違う、背景も違う、一緒に働いてない人たちがチームで成果を出さないといけませんので、コミュニケーションの質がアウトプットの差になっていくとおっしゃってました。
真田:話は変わりますが、以前、有名になったGoogleのアリストテレス・プロジェクトの話がありますね。
辻:心理的安全性と社会的感受性ですね。
真田:それを当時のセミコンダクターさんに当てはめてみた時に、やっぱり同じことが言えるんですか?
辻:それは言えると思いますね。結局トレーニングの規模は何かと言ったら、感受性なんですよ。
つまり、相手の気持ちとかを感じ取る。先ほどの人間関係とコミュニケーションの質で言うと、質の高いコミュニケーションは何ですか?という形で。
みなさんのいろいろな意見を聞いてみると、一番大きいのは自分の考えが通じるとか、相手の考えがわかる、お互い共通の理解が得られるっていうことをおっしゃいます。それをコンテンツでしゃべることは多いです。
つまり、自分の言いたいロジックはこれで、だからそのロジックでやり合ってるんですけどよくよく聞いてみると、中には非常に気持ちが通じたとか、想いがわかったとか。そういうことの方の質が高いという風な人が結構いるという事がわかってきました。
逆に言うと、道理はわかっても気持ちが伝わらなかったら人は動いてくれないということもみんな肌で感じてるわけですよ。
真田:そうですよね。わたしの造語なのですが、論理的納得と心理的納得があるよって話を。
辻:その通りだと思いますよ。
真田:論理的には納得してても心理的に納得してなかったらやっぱりやってくれないですからね。
辻:その心理的納得というところが、みんなすごく難しいと思うんでしょうね。僕の場合は、「わかった」でいいと思ってます。あるいは、この人は自分の気持ちがわかってくれている。厳密に言うと、わかったとはないんでしょうね。
人は一人ひとり違うという前提に立てば、ただ受け止めてくれたと。それはよく夫婦間のけんかの話題にもなるように、気持ちがわからないからというのと同じように。まあ、受け止めてくれたと。批判もしない、反論もしない。ただその前に、この人どういう気持ちなんだろうと感じ取る術がなかったら、それは起きないので。そういう意味ではその部分は大切だなと思いました。
別の言い方をすると、ガミガミ厳しくやってもついていきたくなる上司と、優しくされてもついていきたくなる上司がいるとしたら、その差はやっぱりそのマインドの部分での「わかってくれた」、それが心理的納得かもしれないけれども。理解された、っていう。このスキルの部分では、それこそアクティブ・リスニングは内容と感情のフィードバックなので、必ずその社会的感受性を発揮しなければならないので、自然にそれを鍛えることになるわけです。
心理的安全性ということで言うと、あれは心理的安全性という言い方をしてますが、僕はもう少し踏み込んで言ってもいいと思っています。防衛反応にどう対処するか?と思っているんです。
その防衛反応に対処するスキルが、実はアクティブ・リスニングなんです。
アクティブ・リスニングは本当に単純な方法なので、そこまではと思ってはいたんですけど、よくよくこうやって自分も経験し、職場の人に使ってもらうというのを見てると、やっぱり両方起きるんですよね。防衛反応も静まるし、同時に実はコインの裏表みたいなもので、静まる理由がわかってくれただし、わかってくれたから静まれるっていうことが起きるので。そこがやっぱりカギなのかと。
だからGoogleのアリストテレス・プロジェクトも、考え方を伝えるというところで終わっていますよね。
方法としては、結局あの中のニューヨークタイムズの記事では、ガンかなにかの話をして、全部打ち明けようと正直になって、それで対等に話をするようになったと同じぐらいの時間話すようになったと。
それで自分もそういうことが言える心理的安全性が、そういうことを言った自分の不安などをわかってくれる感受性が大切だというような、ニューヨークタイムズのストーリーだったと思いますけど。
みんなそういうガンにならないと分かり合えないのかと言ったらそんなことはないはずで、何でもかんでも自分のプライベートをさらけ出したら、ああいうことが起きるわけではないので、やはりスキルというところを指摘していないのはなぜかな?と疑問に思っています。
真田:話変わりますが、今独立されてやってる中で、受講者の方はエンジニアの方が多いのですよね。なぜそのエンジニアに受け入れられるのかということをどういう風に分析してらっしゃいますか?
辻:ポイントがあるとしたら、ふたつぐらいですかね。やっぱり、エンジニアも優秀であればあるほど、人間関係の問題だということを気付いていると思います。
真田:気付くんですかねえ?技術にばかり目がいって、人間のことに全く興味がない人もいるような気がしますが。
辻:どちらかというとその割合が大きいのかもしれませんが、技術を突き詰めてそれを形にしよう、つまりチームで動こうということになって、それを追い求めていくと人間関係の問題を避けて通れないということに気付くみたいです。
それでいろんな会社さんでお聞きしてみると、優秀な人であればあるほど、自分でその問題をクリアしているようです。勉強家だから本を読み、自分でコーチングを勉強し。実際にL.E.T.の研修を受けられた方の中で、こちらで見ていても優秀だなと思える方は、こういう感想が多いですよ。
「いろんな勉強をしてきたけど、自分の勉強が間違ってないことが証明されて良かった」と。「いろんなあっちこっちでね、いいとこ取りをしてきたのが整理されて良かった」とか。
やっぱりみんな勉強されてるんですよ。自分なりに。そして実践されてるんですよ。そういうのがまずひとつなんですよね。
自分で勉強される方ならいいのですが、忙しいとかそこは苦手という人も多いんです。
もうひとつは、やっぱりロジックだと思うんですよね。ロジックがしっかりしていると。端的に言うとこうなんです。
例えば、世の中にある普通のマネジメント研修だと、マネージャーは聞きなさいと。聞くことで効果が出るから聞きなさいと。そういう研修をやった時に、僕に出てくる一番多い質問は、エンジニアの方が「いつまで聞いたらいいんですか」と。「いくら聞いても答えが出てこないじゃないですか」と。でも、そういう研修を受けるとひたすら聞けという。やってきましたよと。何も変わらないじゃないですかと。傾聴に意味はないですという声があるんです。
僕は、L.E.T.の中では、「聞けない時は聞かなくていいです、代わりにやることをやってください」と。それもあります、と。「え、何ですか?」とそこで初めてなるわけですね。
ミーシーという表現がありますけどね。やっぱりコミュニケーションのスキルもミーシーであるべきなんです。抜け漏れなく余分なものが見えないように。
ところが、エンジニアの視点で学ぶスキルを見ていくと、穴だらけなわけです。教えられるスキルは。だから信じられないと。
ところがL.E.T.のカリキュラムを見ると、割ときちっとしてるし抜け漏れなく学べると。学んでみたらきっちり論理性がある。因果がはっきりしてる。そういう意味で納得していただけると…。
真田:ロジカルじゃないものはなかなかやっぱり受け止めにくいですね。だから、人間関係とかコミュニケーションに関しても、ロジカルに理解ができた方が学びやすいというか、習得しやすい感じなんですね。
辻:そうなんです。そのロジックもやっぱり人間関係だから、方程式みたいなものではなくてどちらかというと「自分の経験に照らし合わせて納得してもらう」というようなものだと思ってます。彼らも人間なので柔軟性もあります。ただ、真面目に追いかけるから、柔軟性がないように見えてしまう感じがしますけれど、実際のところは、柔軟性も持っていて、ただこの部分はしっかり、技術面はやっぱりこういうきちっとした納得できるストーリーがあればできるよと、わかるよと。そういうのがちゃんとL.E.T.をはじめそういうもの中に組み込まれなければいけないのではないかと思います。
真田:日本を代表するような企業でより高度な技術をやっているところほど、人間関係の問題、コミュニケーションの問題を解決しないと、やはり成果が出せない、それが障害になるという、そういうことなんでしょうか?
辻:そうですね。より顕著だということだと思います。ですが技術の難しさとかそういうのが関係なしに・・・。
そもそも会社というのは人の集まりだという前提に立てば、どこにでも応用できることかなとは思います。
真田:特に技術の世界になってくるとコミュニケーションの問題というと、離職率の問題とかマイナスをゼロにするためにそういうことをしなければならない、というのはあったように思いますけど、より成果を高めるためにも実は大事なんだという文脈で語ることは、そんなに多くなかったような気がしてるんです。
辻:そうだと思います。ネガティブなことが起きないためにやりましょうと。やっぱり成果につながるとは思っていますね。
ただそこの伝え方というのが、実際は成果を上げる直接的なオペレーションがあるわけですからそのオペレーションが評価されるべきなので。そういう意味では、そのオペレーションを支えているもの、一般的な言い方ですが、潤滑油的な役割があったんだというのはそう思いますよね。
これはほんとに実験では調べられないので片方は教えないで失敗させる、片方は…といった実験ができないのは残念ですけど。
ただひとつ言えるのは、会社がたまたま上手くいったんでしょうけども、M&Aで他の文化の人をマージするといった時に感じたことがあるんですけどもやっぱり生産性が変わるような気がします。
言われたからやるという組織の人たちがジョインしてきて教育していくと、自分から動くということに目覚めていく。それは意識ということもあるかもしれないのですが。
真田:それはセミコンでのお話ですかね?
辻:はい。大手のメーカーさんがジョインしました。僕もそのお手伝いにいったのですが、研修をするともう拒絶からスタートします。SONYのなんだよ~みたいなのが来ますから、俺たちは上手くやってんだ~と、ずーっとやると、あ、自分たち全然やってなかったねって
真田:それぞれの企業の文化に、そんなにこう距離があるというか…
辻:ありますね。SONYはとにかく任せたらやって、の世界ですけど、大手のメーカーは上からやりますからね。
真田:そうなんですか。
辻:今もそうですが、本社から来たマネージャーは、ほんとにえらそうで権限を持っているんです。「君たちは言われた通りにやるのが仕事だ」という世界ですから。今問題起きてるじゃないですか。いろいろな企業で粉飾決算などの問題は噴出しているということも含めて。そういうことが起きる世界だな、と思ってます。
生産性とは何か、というところのひとつの問いかけには、エンジニアの方々に届くんじゃないですかね。エンジニアにとっての生産性は何かと言えば、一人ひとり考えがあって、たくさん売れるのは結果であって、自分のアイデアが形になる、実現する、世の中に生かされる、というのも、彼らにとってはアウトプットなので。その中で人間関係に気付く、という感じだと思います。
真田:なるほど。今日はお忙しい中、さまざまなお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
辻:はい、こちらこそありがとうございました。