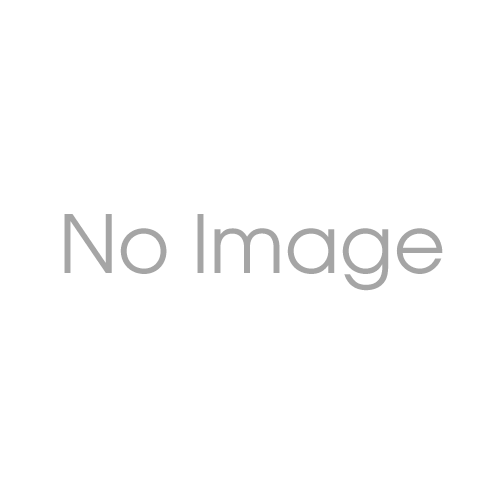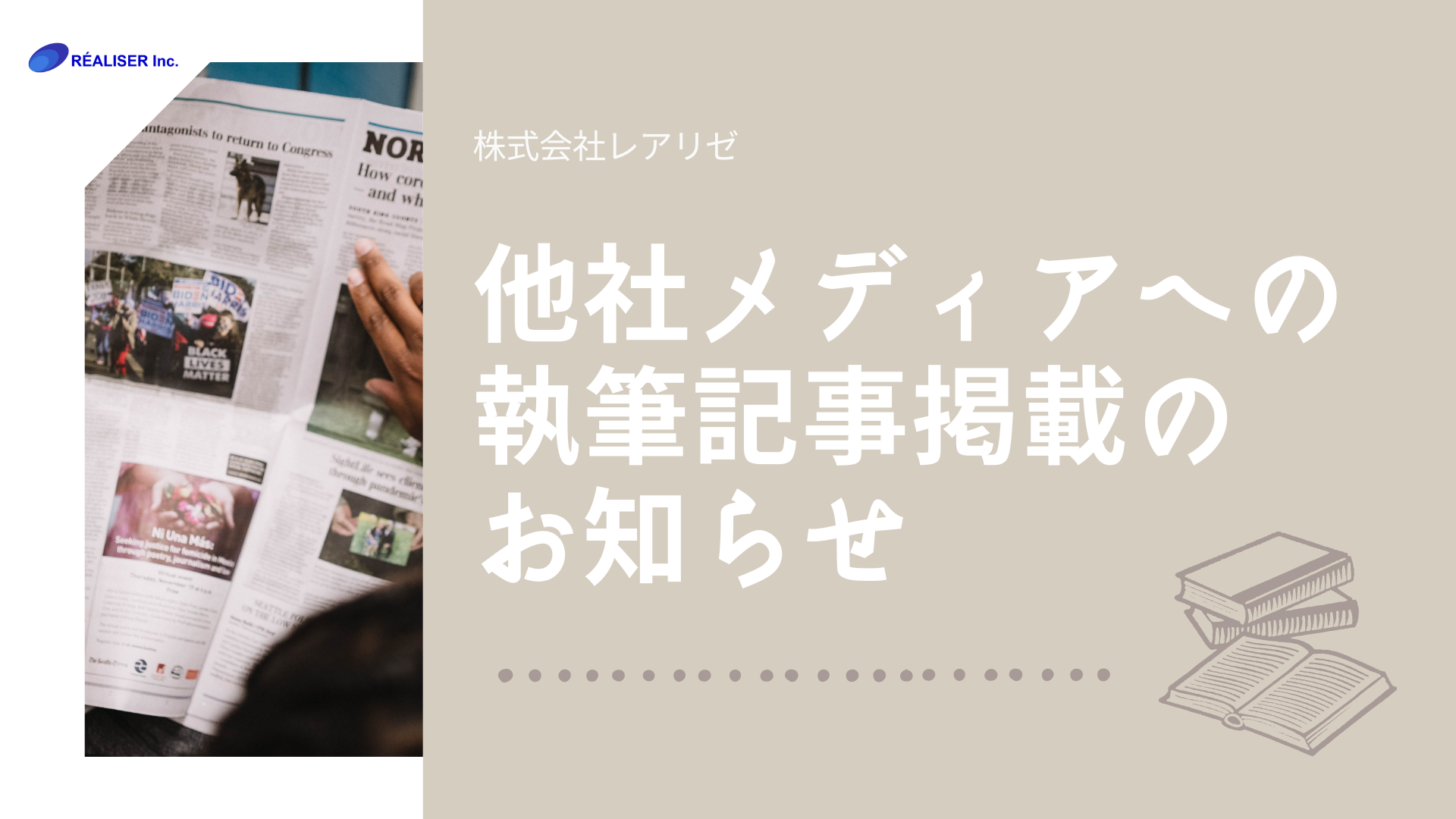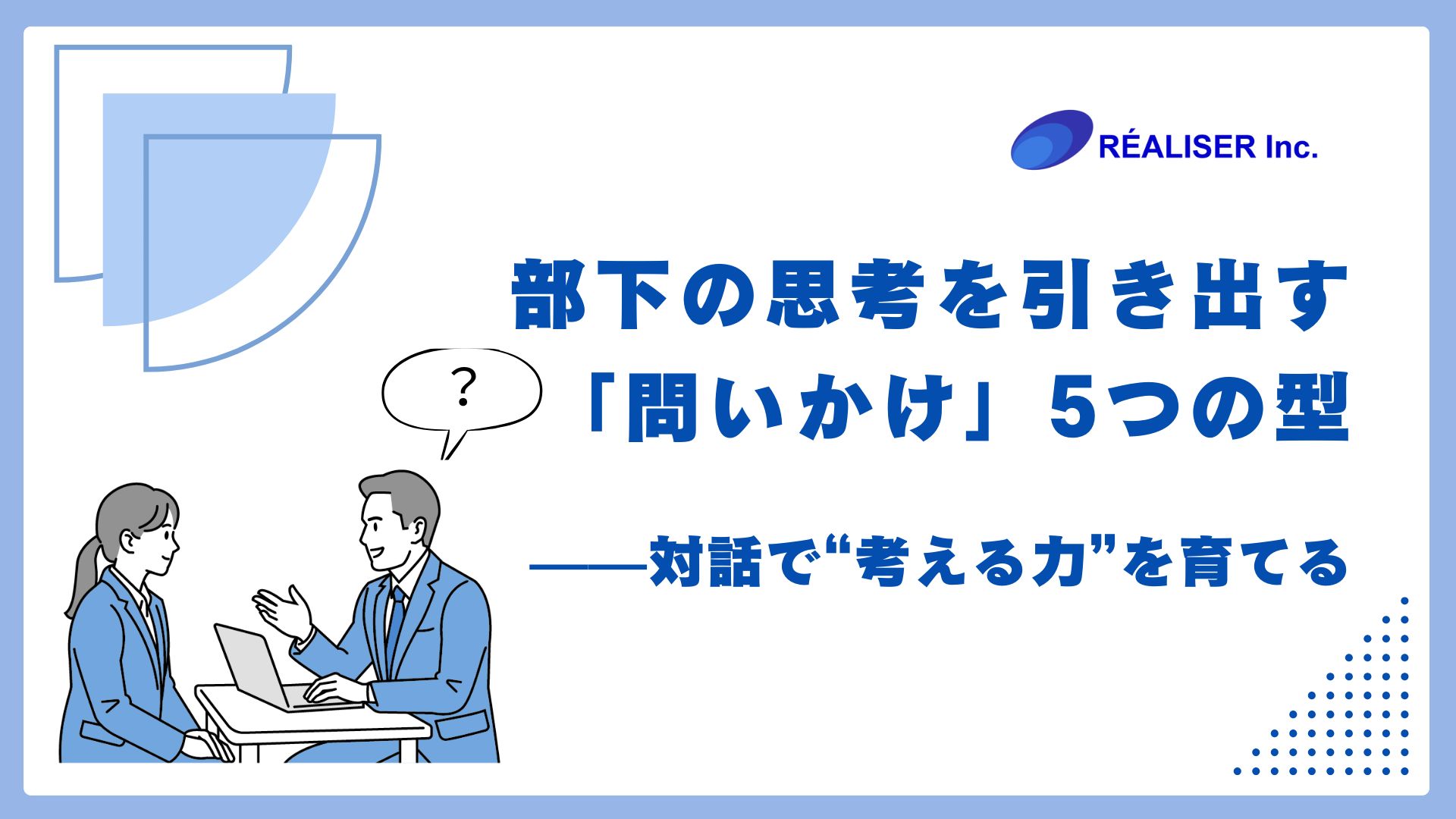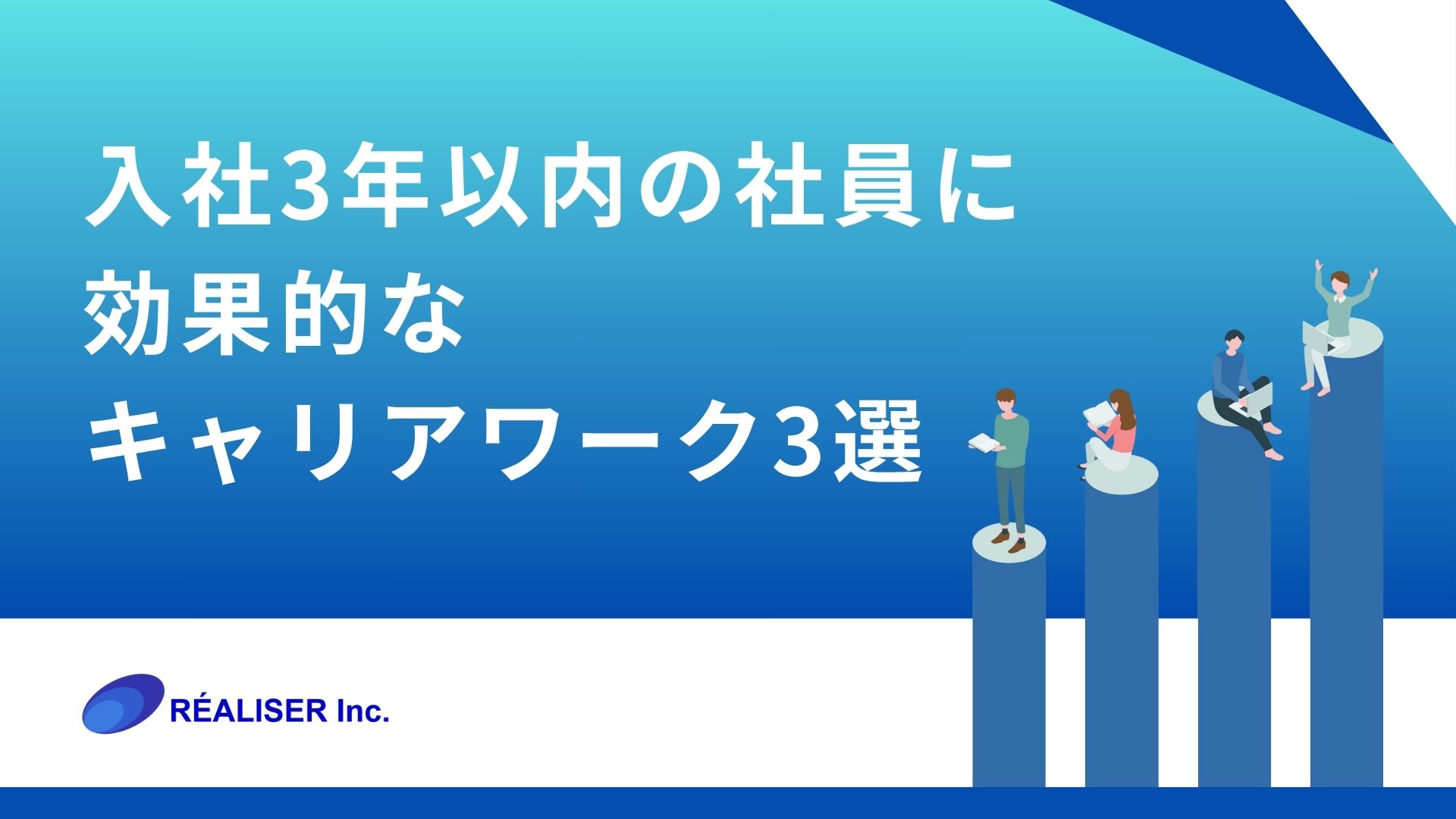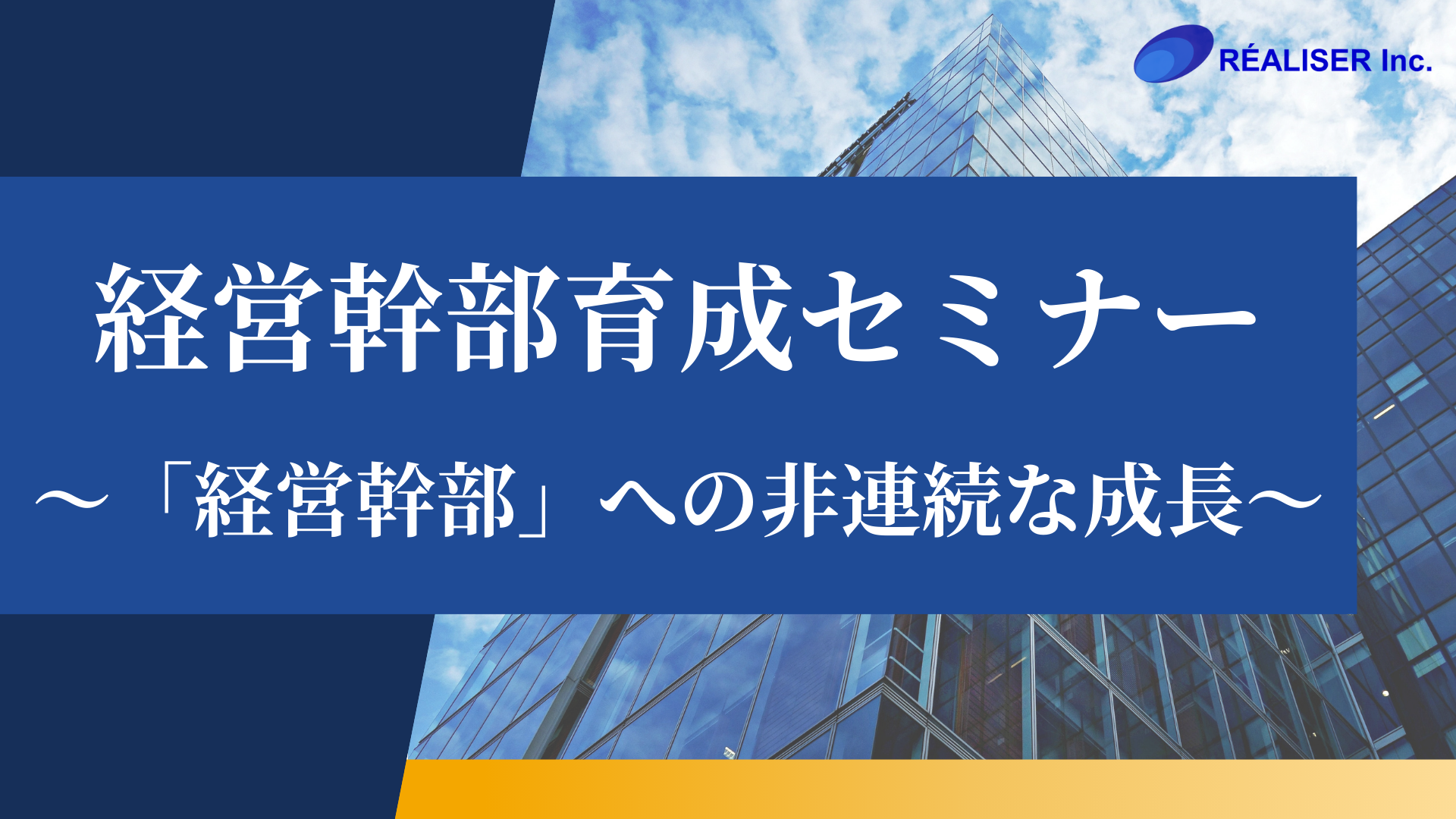適応・進化能のある組織
1.情報化時代の組織の特徴
現代社会は、インターネットの普及に伴って情報化の波が激しさを増しています。未来の予測は困難を極め、不確実性も高まっています。こうした社会環境の変化に伴って、企業の組織づくりも、従来とは異なる視点で行わなければならなくなってきています。
それでは具体的に、どのような点に注目する必要があるのでしょうか?
結論から言えば、情報化社会を生き抜く組織には、次に挙げる2つの力を備えることが求められるでしょう。
1つは、外部環境の変化に対して素早く柔軟に対応出来る適応力、もう1つは、環境の変化を捉え、能動的に進化する創造力です。
これら2つの力を備えた組織は、予め精密に計画設計された機械的なものではなく、外部環境を認知し学習して、自己組織化する生物的な特徴を持つものになると考えられます。
企業組織は、社会システムという広い観点からから見ると、社会という生態系システムの一部を構成する要素ということができます。ですから、その時代の社会環境に生存するためには、その環境に合った組織のあり方が求められます。
2.社会の構造変化がもたらす組織への影響
未来学者のアルビン・トフラーは、『第三の波』の中で、社会変化を三つの波になぞらえて表しています。
第一の波は、農耕革命と呼ばれるものです。これは、約一万年前に人類に起きた革命であり、それまでの狩猟採集社会から農耕社会への移行に伴う社会的変化です。農耕革命によって、生活スタイルは移動型から定住型になりました。また、作物の計画生産が可能となり、土地を所有し経営する者と雇用される者の関係が生まれました。
第二の波は、産業革命です。これは、およそ18〜19世紀にかけて起きた農耕社会から産業化社会への変化によって起きたものです。産業化社会は工業化社会とも呼ばれ、再生不可能な化石燃料をエネルギー源として、大量生産と大量消費の流れを作り出しました。この時代には、フレデリック・テイラーによって考案された科学的管理法が組織のあり方を大きく変え、ヒト・モノ・カネをいかに計画的に管理するのかが重要な課題になりました。
そして第三の波は、20世紀中盤から始まった情報革命です。情報革命によってもたらされた情報化社会の目覚ましい進歩は、コンピュータの開発と技術進歩とインターネットの普及によって支えられています。これにより時間と空間の壁は取り払われ、飛躍的な速さで社会が動くようになりました。社会が認める価値は、モノから情報へとシフトし、未来の予測困難性と不確実性が高まりました。
こうした時代の変化の中で、組織のあり方も変化することが余儀なくされています。工業化社会の組織は、管理に力を注いできました。工業化社会の価値の中心であったモノは管理できるものだったからです。
しかし、情報化社会になると、管理できるモノとは異なり、管理できない情報を扱わなくてはならなくなりました。その結果、情報化社会の組織は適応と創造に力を注ぐことが求められるようになってきています。
3.モチベーションのバージョンアップ
また組織行動を考える上で、人間の行動の源泉となるモチベーションの影響も無視することはできません。社会的な変化は、人間のモチベーションにも大きく影響をもたらしており、時代と共に何を重視するのかが変わってきています。
ダニエル・ピンクは、学習心理学の知見を援用しながら、人間を取り巻く社会背景を反映させた形でモチベーションを3つの類型で表しました。これらは、コンピュータのオペレーションシステムになぞらえて、次のようにバージョン1.0から3.0に分けられています。
〈モチベーション1.0〉
原始時代に人間社会を支配していたモチベーション。生存を目的とする人類最初のオペレーションシステム。
〈モチベーション2.0〉
工業化社会を支配していたモチベーション。アメとムチに例示されるように、報酬と懲罰というような外部からの刺激によって人を動機づけようとするオペレーションシステム
〈モチベーション3.0〉
情報化社会に求められるモチベーション。自己決定と自己選択、学習と成長、創造や社会貢献など、内発的動機付けを基礎とするオペレーションシステム。
情報化社会において重視されるようになったモチベーション3.0は、自律性、マスタリー(熟達)、目的という3つの要素から構成されています。これは、情報化社会の中で働く人々の行動を理解する上で注目すべき点であり、組織づくりをする際の検討課題となるべきものと考えられます。。
4.機械的組織から生物的組織へ
トフラーが示した社会構造の変遷とピンクが示したモチベーションの変化を重ね合わせてみるとあることが見えてきます。それは、工業化社会に用いられていたヒエラルキー構造に代表される機械的な組織デザインはモチベーション2.0で動く人々を対象にしており、内発的動機付けによるモチベーション3.0で動く人が増えた情報化社会においては機能しないということです。したがって、これからは、これまでにない新たな組織づくりのフレームが必要となります。
近年、生物的な特徴を持つ組織モデルが注目されるようになりました。その1つにホラクラシーと呼ばれる組織モデルがあります。
ホラクラシーは、権限と情報の流れを階層構造によりコントロールするヒエラルキー構造ではなく、権限と情報を開放してメンバーが自律的に意思決定し行動できるよう構造化された分散型・非階層型の組織モデルです。企業の導入例としては、ザッポスやAirbnb、ブラジルのセムコなどが挙げられ、日本でもダイヤモンドメディア株式会社が設立当初からホラクラシーに取り組んでいます。
このような組織づくりは難易度が高く時間もかかりますが、自律的で主体的な組織活動を生み出す効果があるため、採用する企業が増えてきています。
2015年5月22日に発行された『THE WALLSTREET JOURNAL』によれば、「アメリカではこの10年ほどで300社が取り組み、そのうち1年間採用した企業は80%を占める」という内容の記事が掲載されました。
今後このような自律分散協調型の組織は情報化社会の生態系の中で確実に増えていくことでしょう。
5.これからの組織づくり
オックスフォード大学のマイケル・オズボーンらは、2013年に発表した論文で今後10〜20年程度で、米国の総雇用者の約47%の仕事がAIなどにより自動化されるリスクが高いと指摘しています。これを受けて野村総研が日本国内601種類の職業を対象に試算した結果、日本の労働人口の約49%の人々の仕事がAIに代替される可能性があると推計しました。
今後は、検索や計算や分析などAIが得意とする業務は自動化され、人間は感性や創造性を活かした仕事を協働しながら進めていくことが重視されると考えられています。こうした働き方を可能にするためには、機械的な組織から生物的な組織組織への移行が必要です。
情報化社会を生き抜く組織には、2つの力が必要です。
1つは、外部環境の変化に対して素早く柔軟に対応出来る適応力、もう1つは、環境の変化を捉え、能動的に進化する創造力です。
組織づくりを行う際には、この2つの力の向上を目指して、メンバーの強みを活かし、組織の学習力を高め、働く喜びとやりがいを生み出す工夫が求められるのでしょう。

渡邊 義
ウェルビーイング心理教育アカデミー共同代表理事
SmartBeing合同会社代表、神栄カウンセリングセンター所長