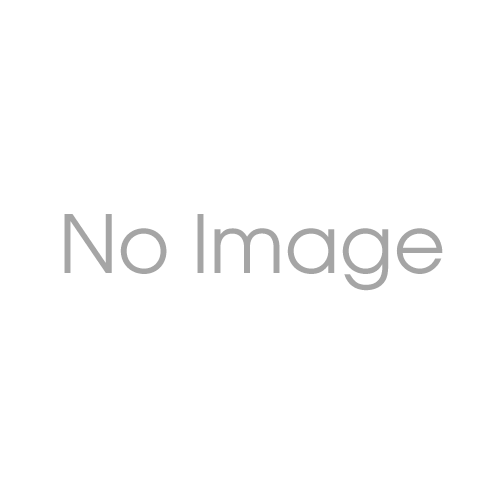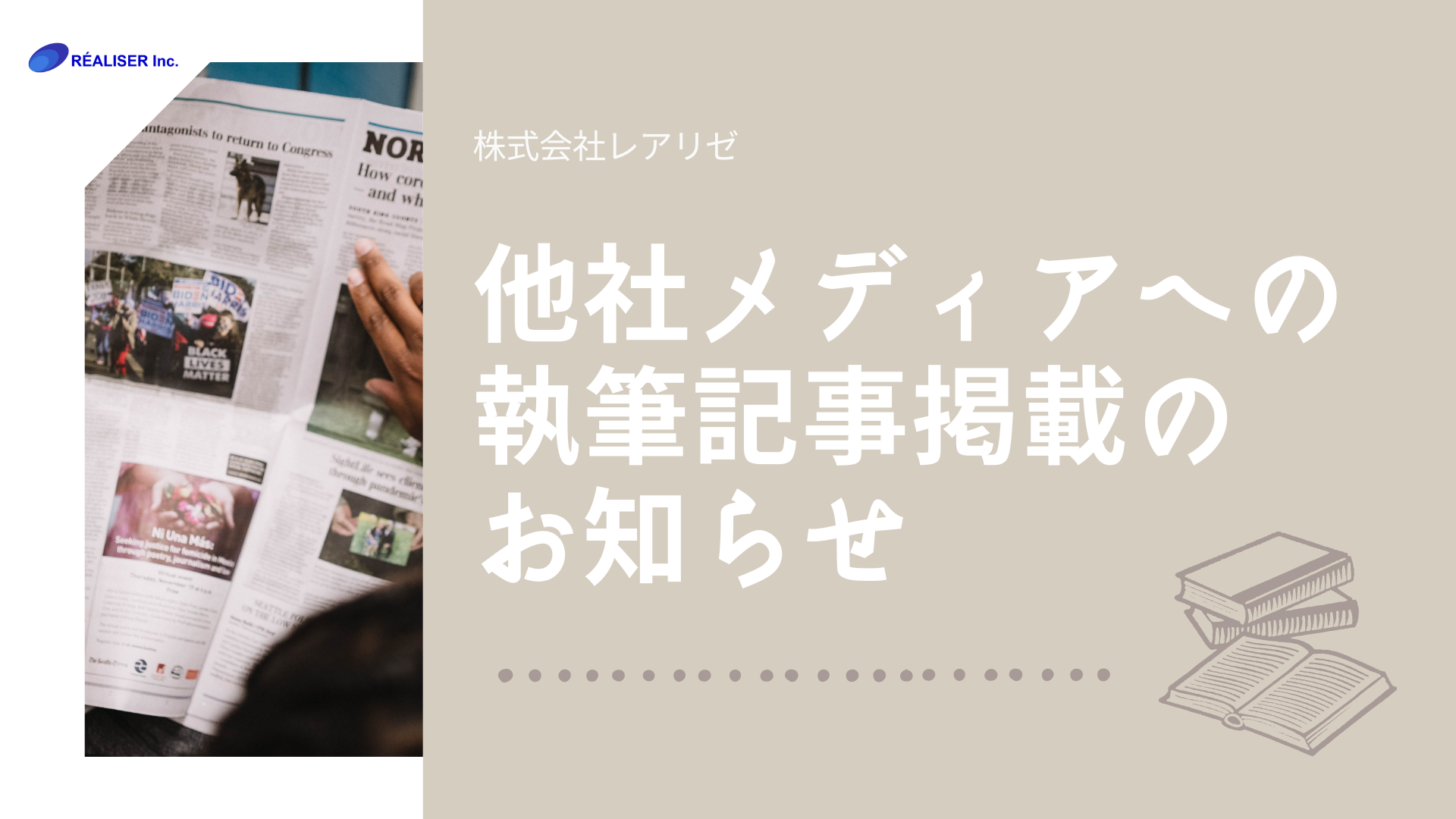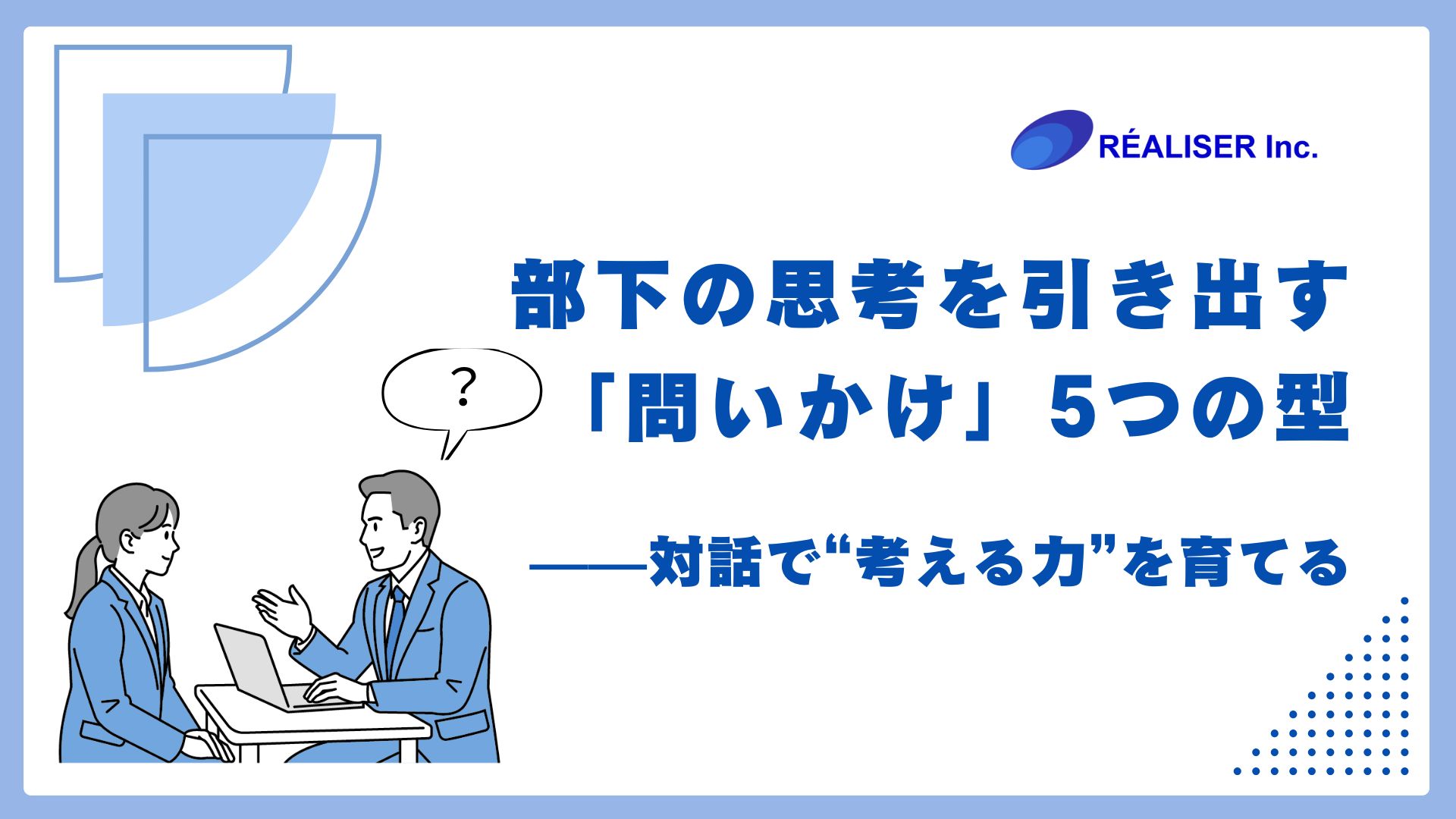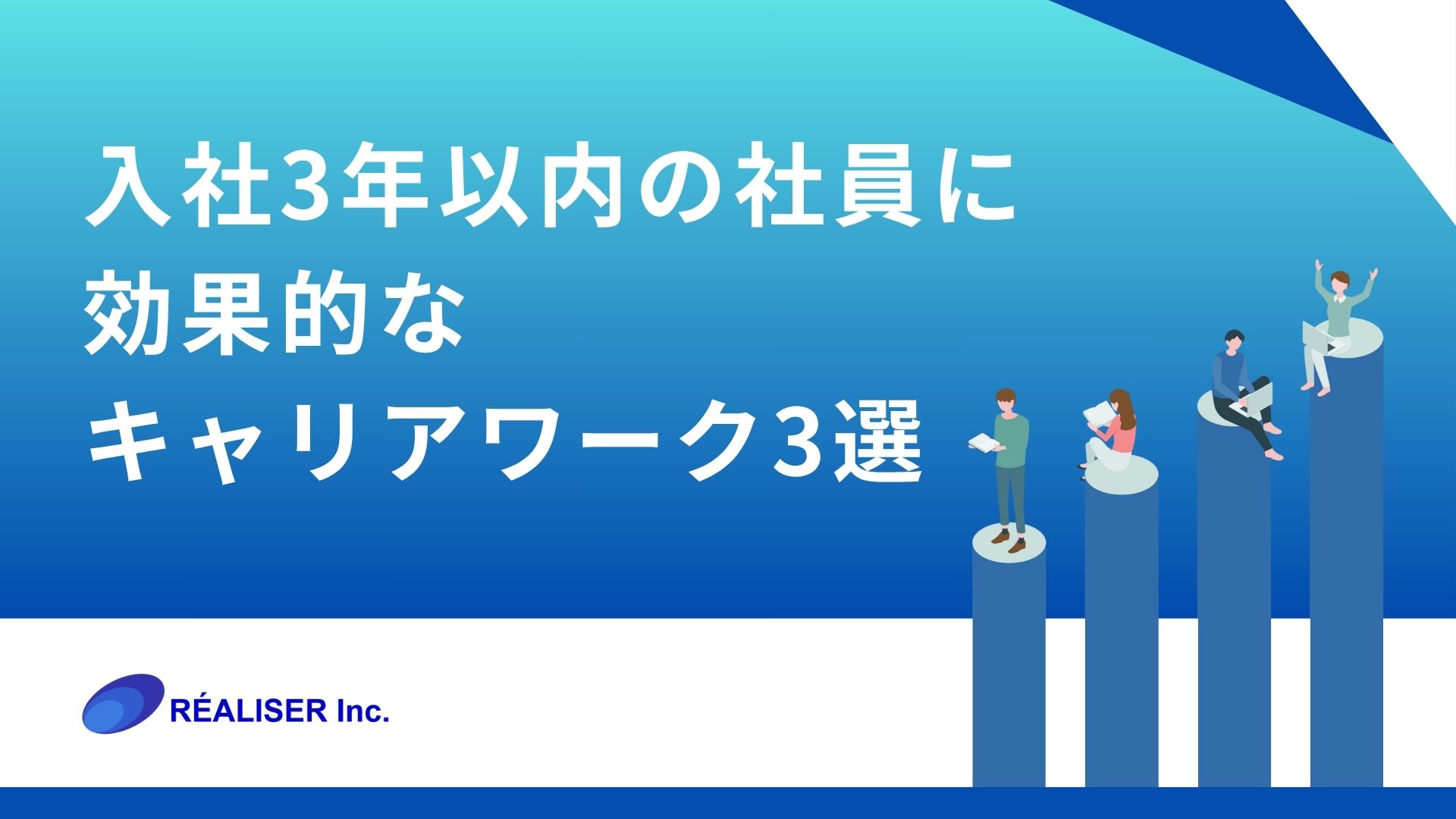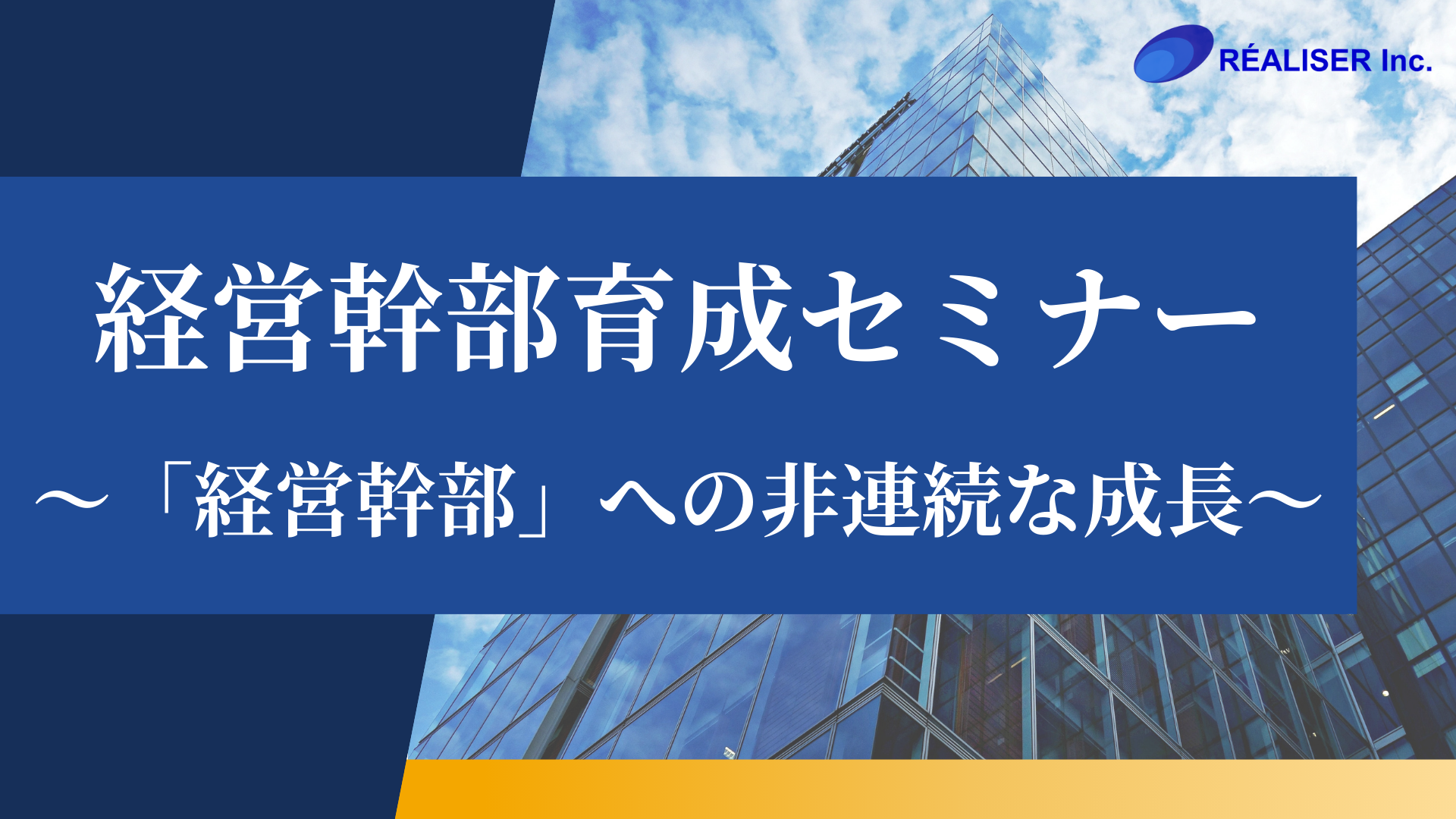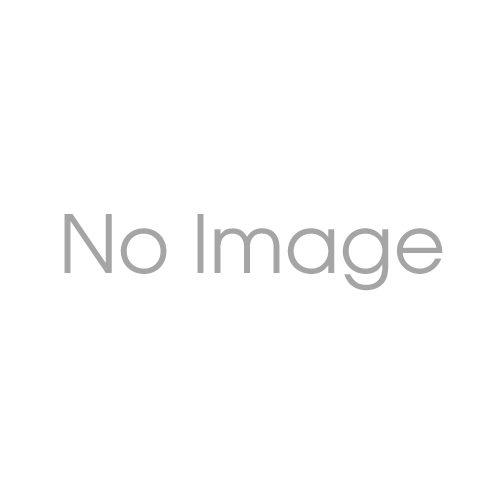
第2回サーバントリーダーシップフォーラム
~ サーバントハートが組織を強くする ~
ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役社長
木川 眞 氏
「為さざるの罪」
~ヤマトグループのDNAと現場力を引き出すリーダーシップ~
2012年10月22日に行われた「第二回サーバントリーダーシップフォーラム」。
参加者の皆さんにサーバントリーダーシップについて考えて頂くことを目的として、毎回 各界のリーダーをゲストとしてお招きし、ご講演頂いています。
ゲストの中には、日頃からサーバントリーダーシップを意識して実践していらっしゃる方もいれば、ご自身では「サーバントリーダーシップ」という言葉は意識していないものの、自然とサーバントリーダーシップを実践していらっしゃる方もいます。
今回は、ゲストの1人であるヤマトホールディングス株式会社 代表取締役社長 木川 眞 氏の講演レポートを掲載させて頂きます。
1.登壇者情報

木川 眞氏
ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役社長
1949年、広島県生まれ。1973年一橋大学商学部卒業後、(株)富士銀行入行。1998年人事部長、2004年4月(株)みずほコーポレート銀行常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員。2005年4月ヤマト運輸(株)グループ経営戦略本部長、同年11月、ヤマトホールディングス(株)代表取締役常務。2007年3月代表取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員。2011年4月より現職。※部署・役職はインタビュー当時のものです
2.講演レポート
「為さざるの罪」~ヤマトグループのDNAと現場力を引き出すリーダーシップ~」
ヤマトグループは、1919年に日本で最も古い民間の運送事業者として創業されました。今や小笠原諸島などを含む全国に拠点を置き、日本人になくてはならないインフラとなり、その中で我々は社会のために何をすべきかを考えなければならない立場になっている、と言えるでしょう。
創業から10年目に路線事業開始という第1のイノベーションを起こしましたが、その後約50年間は大きな改革ができず、世間で「倒産するのでは?」と囁かれるような危機にも直面しましたが、そこで第2のイノベーションとして、1976年、当時の社長であった小倉昌男が新事業へのチャレンジである「宅急便」を開始しました。そして今、第3のイノベーションを起こそうとしています。
現在の経済環境や少子高齢化において、今の事業構造に依存していては、企業は衰退してしまいます。ヤマトグループは7年後に創立100周年を迎えます。そのとき我々はどんな企業でありたいのか―。
当社のステークホルダーである「お客様」「社員」「社会」「株主」の満足度の総和を上げて行く、そしてこれからの時代により一層大切にしなければならないのは「社会」であると思っています。社会で一番愛される企業になるために、3つの改革(事業構造改革、業務基盤改革、意識改革)を進める「DAN-TOTSU経営計画2019」を、昨年2月に発表しました。
アジアを中心とした海外における宅急便の事業展開を進め、国内では既に出来上がっている宅急便のネットワークインフラを活用して地域密着型のサービスを展開していきます。
地域活性化のための新たな取り組みもスタートしています。当社が持つネットワークを含めたインフラを開放し、地域の民間企業、行政、住民、生産者、NPOに利用してもらうことで、地域経済や商店街の活性化、住民の生活支援を実現し、「新しい公共」を創るということです。
行政との協業による地域活性化の事例としては、岩手県で高齢者の生活支援を行なっている「まごころ宅急便」や、鳥取県境港での地元企業、行政、ヤマトグループが三位一体となった「山陰流通トリニティセンター」によって地元企業支援を展開しています。
そして、これらは単なるボランティアではないということです。ボランティアという軸足では長続きさせることは困難です。我々は営利企業として事業化できないとなりませんが、受益者が必ずしも高い対価を払って頂けるものではないので、広く浅くそして時間的に長く、少しずつ利益を出し合い、参加者を多く募り、共存するという全く新しい事業創造へのチャレンジなのです。
こうした事業戦略で進めて行こうとした矢先に、3.11の震災が起きたわけです。
従って、我々の事業戦略と震災での活動というのは表裏一体で、その時に取ってつけたものではなく、自然の流れからあのような活動になったことが多くあります。
1.現地での救援物資輸送協力隊
震災直後、地元社員が自発的に各自治体に救援物資の輸送協力を申し出て、活動を行っていました。後日、その情報を本社が知り、この取り組みを追認する形で会社として車両200台、人員500名を組成し3月23日から開始しました。
2.「宅急便1個につき10円」の寄付
1年間実施した結果、約142億3600万円となり、これは当社の年間純利益の約4割に相当する額となりました。寄付先を農業、水産業、生活基盤に指定したために、当初は全額課税と言われましたが、財務省と交渉した結果、指定寄附金に指定していただくことにより、全額無税で寄付をすることができました。この仕組みは、今後日本で企業が多額の寄付を行なう新たな文化になるきっかけになったと思います。
寄付先は、今やらないといけないことに特化し、見える支援・速い支援・効果の高い支援を選定基準としました。例えば、南三陸の仮設魚市場の建設や岩手県野田村の流失した保育所を安全な高台に再建する、といった国ができないことを中心に助成を行なっていきました。
では、なぜこのようなことができたのか?それは企業風土の裏付けがないとできないものであると、私は信じたいです。当社には創業以来、3つの社訓があります。
一、運送行為は委託者の意思の延長と知るべし(サービスが先、利益はあと)
一、思想を堅実に礼節を重んずべし(コンプライアンス)
この社訓が具体的な行動に表すとどういうことなのか、会社や経営者が実際に社員へ見せるチャンスは殆どないものです。しかし、3.11の震災で社員が自発的に動いてくれたこと、そして会社は寄付と言う形でそれに答えたこと― その時の社員の気持ちを大切にし、社員がやりたいことを会社として追認することで、見せることができたと思います。
私は、社員に対して常日頃言ってきているのは「為さざるの罪」です。やらないで平穏無事に過ごすのではなく、絶対にやるべきだと思うなら失敗しても良いからチャレンジすることだと。結果が悪くても会社は認めるから、それを踏まえ再チャレンジすれば良い、と伝えています。
では、そのような社員をどのように育成してきているかということの一端が、この「感動体験DVD」でご覧頂けると思います。(DVD上映)
社員が企業の価値観を如何に共有できるかということ、また、仕事は「世のため人のため」であるということを言い続け、それを見せるチャンスがあれば見せるということ、そしてそれを決して「施し」ではなく、日常的な事業の中にそういう考え方を如何に埋め込めるかが重要だと感じています。
3.サーバントリーダーシップについて
今後、企業が継続的に発展していくために必要な考え方の1つとして、レアリゼではサーバントリーダーシップを推奨しています。
2004年にはNPO法人日本サーバント・リーダーシップ協会を設立。レアリゼ代表の真田が理事長を務め、レアリゼが事務局を担っています。

当webサイトにはサーバントリーダーシップのまとめページを設置していますので、是非そちらもご活用ください。