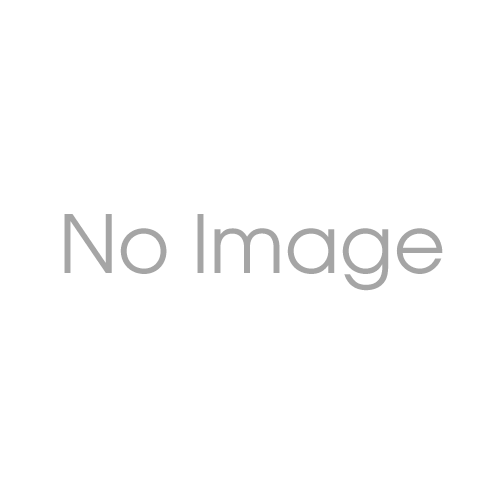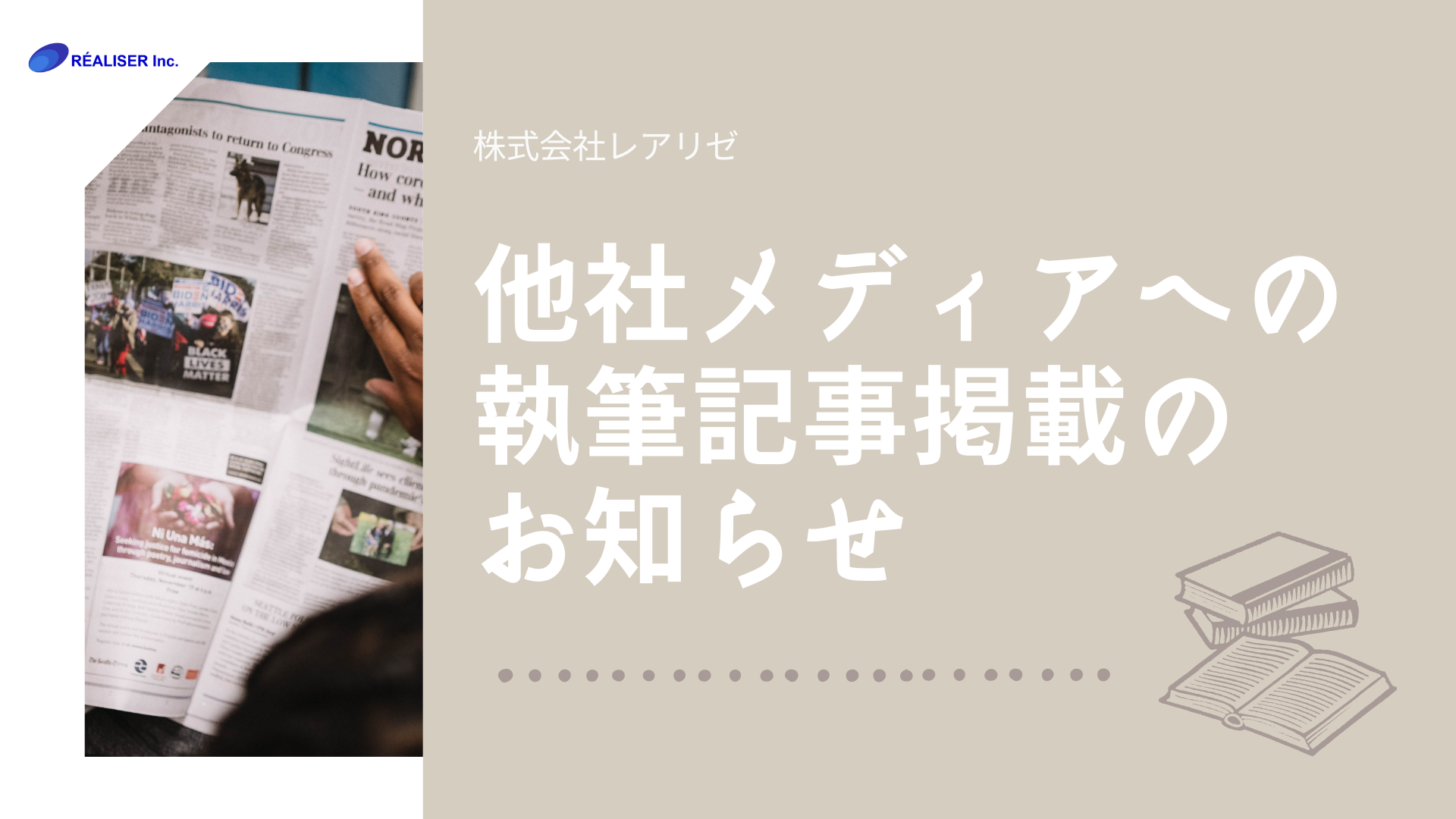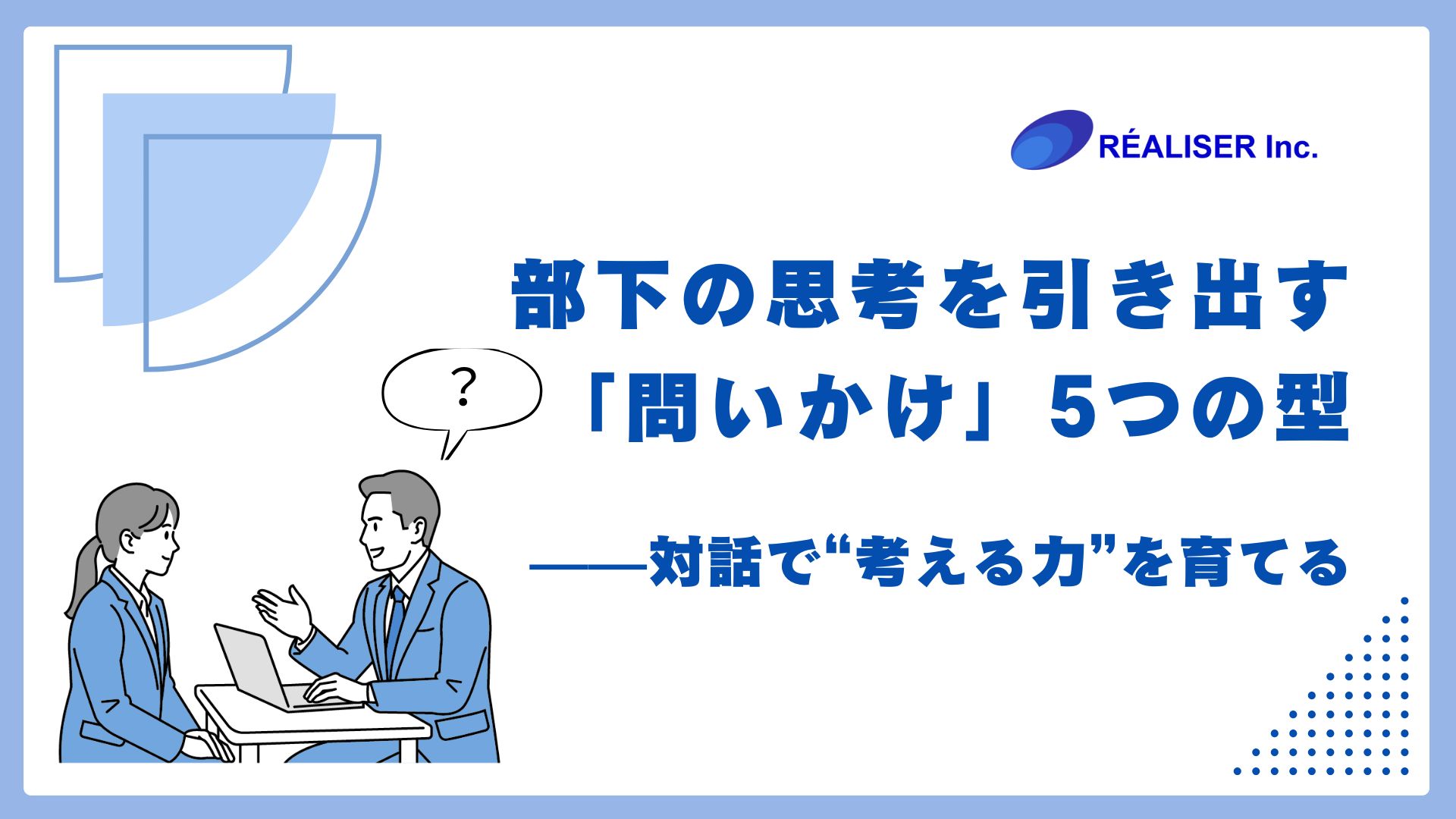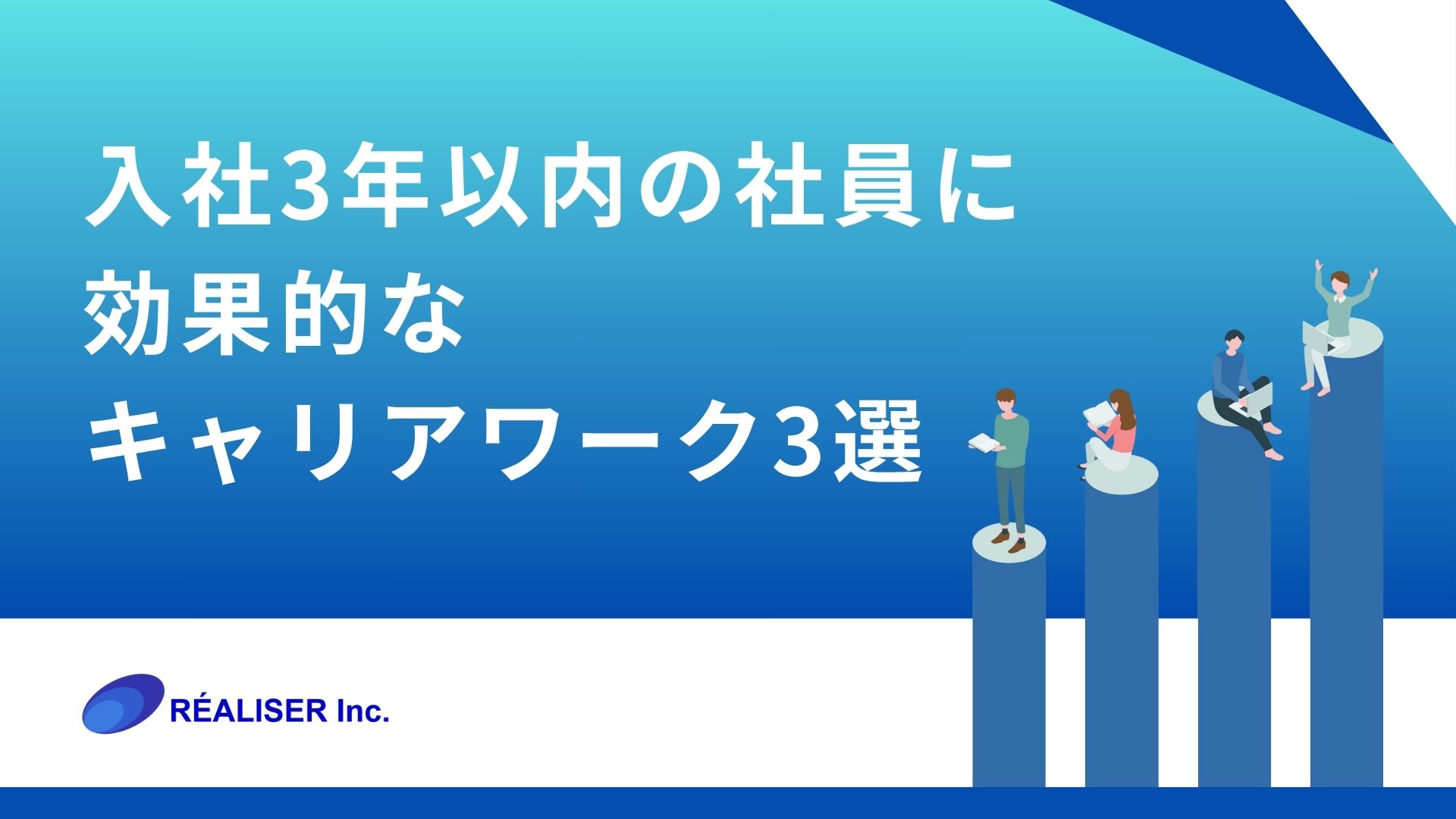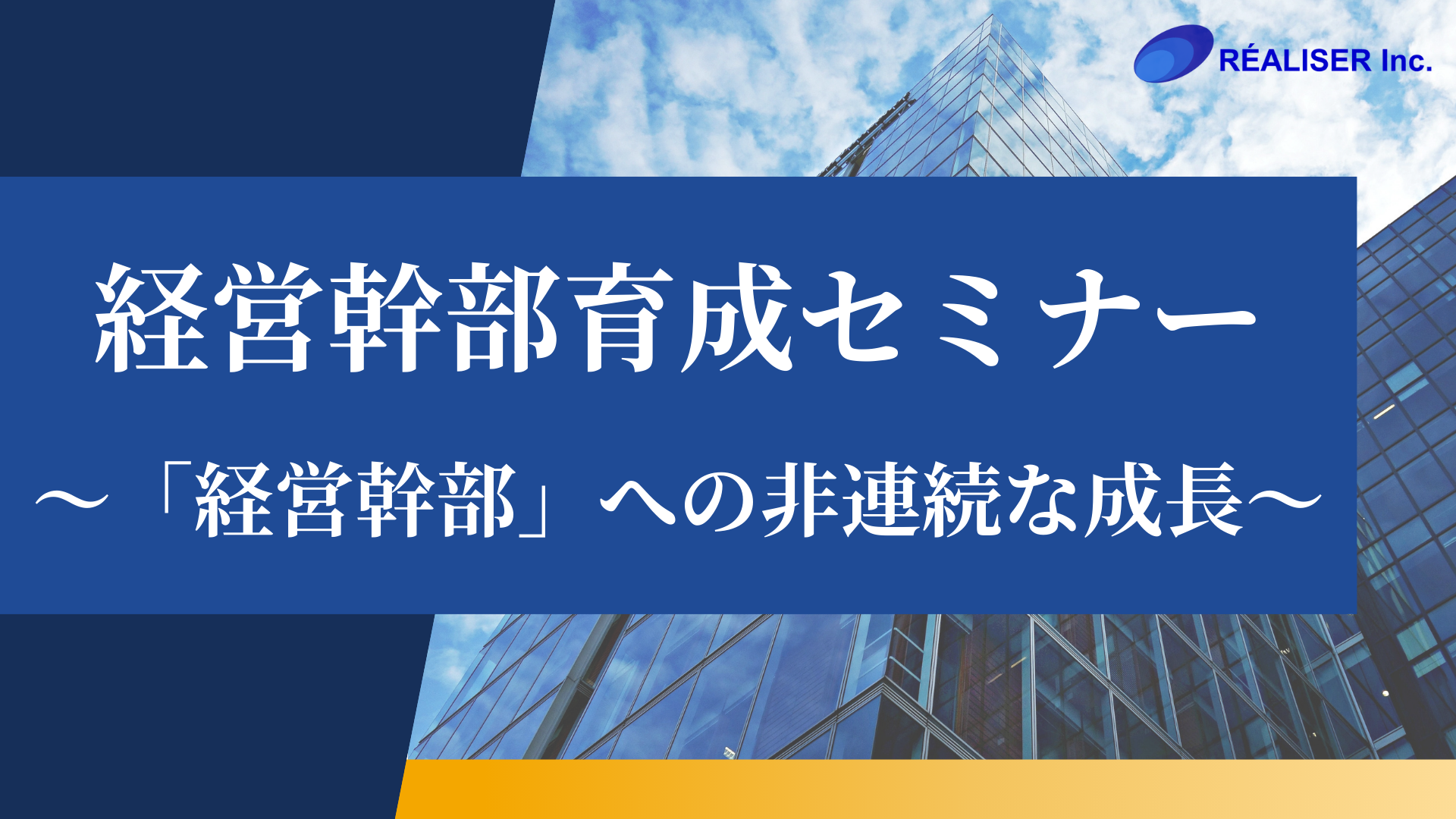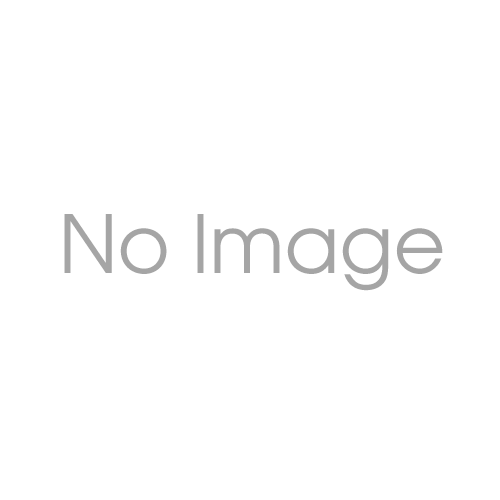
第3回サーバントリーダーシップフォーラム
~ 『いい組織』を創るリーダーシップとは ~
日本マイクロソフト株式会社 代表執行役社長
樋口 泰行氏
「時代が求めるリーダーシップ」
2013年5月30日に行われた「第3回サーバントリーダーシップフォーラム」。
「いい組織」「いい会社」には、それを可能にするリーダーシップが存在します。トップはもちろんのこと、組織を動かす一人ひとりがどんなリーダーシップを発揮することが必要なのでしょうか。サーバントリーダーシップはきっと大きなヒントとなるでしょう。
参加者の皆さんにサーバントリーダーシップについて考えて頂くことを目的として、毎回 各界のリーダーをゲストとしてお招きし、ご講演頂いています。
今回は、日本マイクロソフト株式会社 代表執行役社長である樋口 泰行氏の講演レポートを掲載させて頂きます。
1.登壇者情報

樋口 泰行 氏
日本マイクロソフト株式会社 代表執行役社長
大阪大学工学部、ハーバード大学経営大学院卒業。日本ヒューレット・パッカード代表取締役社長 兼 COO、株式会社ダイエー 代表取締役社長兼 COOを経て、マイクロソフト株式会社に代表執行役 兼 COOとして就任後、2008年マイクロソフト コーポレーションコーポレートバイスプレジデント 就任、現在に至る。※部署・役職はインタビュー当時のものです

ファシリテーター 鈴木 寛 氏
参議院議員・元文部科学副大臣
東京大学法学部卒業後、通商産業省を経て、中央大学講師、慶應義塾大学助教授。2001年東京選挙区で参議院議員に当選。2009年から2年間、文部科学副大臣を務め、2011年野田佳彦内閣の発足に伴い、民主党政策調査会副会長などに就任。2012年12月から民主党広報委員長を務めるほか、中央大学、大阪大学、電気通信大学、東京大学などでも教鞭をとる。※部署・役職はインタビュー当時のものです
2.講演レポート
「時代が求めるリーダーシップ」
■経営者として大事な3つのこと
1)健全なる企業文化をつくる 企業文化が不健全であると、世の中のトレンドや悪い情報がなかなかトップに伝わらず、企業としてのダイナミズムがなくなってきます。
企業文化が不健全であると、世の中のトレンドや悪い情報がなかなかトップに伝わらず、企業としてのダイナミズムがなくなってきます。
ダイエーは長年、店頭に並ぶ「野菜の鮮度の悪さ」が問題とされてきました。ところが、危機意識の欠如、他責意識、一部の実力者に偏った発言権など、不健全な文化が解決を遅らせていました。
そこで全部署から、野菜の鮮度改善に取り組みたいと本気で思っているメンバーだけを集めて、プロジェクトチームを組みました。
私はすべてのミーティングに参加して、年齢も役職も性別も関係なく、ダイエーを良くしようとする意見をどんどん言わせました。そうしなければ、ベテランやポジションのある人しか物を言えないからです。何か言いたいけれども言えずにいるメンバーを指して、私が話をさせることも度々ありました。
それでも長年の体質は簡単には変わらず、何度も挫折しかけましたが、このプロジェクトひとつできないのなら、この先ダイエーは何もできないだろうと思い、デッドラインを決めて必死に取り組みました。結果として、だんだんとチームワークが発揮され、最終的にはお客様に対する大々的な「野菜の鮮度宣言」を経て、お客様からの信頼を回復するに至りました。これは健全なる企業文化の実現に向けて、非常に大きな一歩だったのではないかと思います。
2)社員力を高める
さらに、赤字で閉鎖することになった全国50の店舗をほぼ全て回りました。周囲からは批判もありましたが、私はただ、店を閉める理由を直接説明したい、長年働いてくださった方に一言お礼を伝えたいという一心でした。閉鎖店舗では、社員やパートのほとんどの人たちが涙を流し、時にはなじられることもありました。しかし、励ましに行ったつもりが逆に励まされることもありました。
意図していなかったのですが、結果的に、彼らがその後張り切って頑張ってくれたおかげで、閉鎖店舗の最後の売り尽くしセールで、2年4ヵ月ぶりの前年比プラスを実現させました。さらに閉鎖店舗から継続店舗に配置転換になった社員の方が「店が赤字になってはダメだ、みんなで頑張ろう」と言って回ってくれたこともあり、継続店舗の社員も意地を見せようとモチベーションが一気に高まりました。その結果、継続店舗も11ヵ月連続で前年比プラスを達成したのです。これが社員力であり、社員はモチベーションが上がった時には大変な力を発揮するものだと思いました。
3)経営者としての戦略 現状のビジネスモデルで利益を出すのが苦しい場合、経営的余裕がある間に、違う戦略的柱を立てなければなりません。戦略的転換をする時には、社員がなかなかついて来られない場合もあります。そういう時は、遠くが見えている経営者が大きく舵を切るのも責任だと思っています。
現状のビジネスモデルで利益を出すのが苦しい場合、経営的余裕がある間に、違う戦略的柱を立てなければなりません。戦略的転換をする時には、社員がなかなかついて来られない場合もあります。そういう時は、遠くが見えている経営者が大きく舵を切るのも責任だと思っています。
一方で、自ら現場に赴き、何が起こっているかを確認し、セクショナリズムがあったら自ら取り除くことも重要です。「アクセスしやすい自分」にならなければ、社員は話をしてくれません。
社員に共感するためには感受性を高めることも必要です。一方でそれに引っ張られすぎると経営の優先順位を誤ってしまうこともあります。人に優しいだけの「いい会社」を創っても、これからのグローバル競争の中では生き残っていけません。今後もそのバランスを取っていかなければいけないと考えています。
3.サーバントリーダーシップフォーラムについて
■サーバントリーダーの発掘
サーバントリーダーシップとは、もともとロバート・K・グリーンリーフ氏(1904~1990)が提唱した「リーダーである人は、まず相手に奉仕し、その後導くものである」というリーダーシップの実践哲学です。 ここ最近では、サーバントリーダーシップを実践して、成功を治めている企業やビジネスリーダーが増えています。アメリカでは、スターバックスやサウスウエスト航空、P&G、日本では資生堂がサーバントリーダーシップの実践企業として有名です。しかし残念ながら、日本において他企業の名前はまだあまり出てきません。
ここ最近では、サーバントリーダーシップを実践して、成功を治めている企業やビジネスリーダーが増えています。アメリカでは、スターバックスやサウスウエスト航空、P&G、日本では資生堂がサーバントリーダーシップの実践企業として有名です。しかし残念ながら、日本において他企業の名前はまだあまり出てきません。
そこで私たちは、サーバントリーダーシップを発揮して活躍なさっているリーダーの発掘に努めています。そうしたリーダーのリーダーシップに対する考え方や実践の効果を、多くの方に知っていただくことで、サーバントリーダーシップを意識するリーダーを増やしたいと考えています。
■サーバントリーダーは何に奉仕するのか
サーバントリーダーが「メンバーに奉仕する」ということは知られていますが、実際はメンバー以外に、ミッションやビジョンにも奉仕しています。サーバントリーダーシップの根幹にあるのは、人の役に立ちたいという「利他」の心です。サーバントリーダーはまず、人の役に立つミッションやビジョンを描き、その実現のためにメンバーや関係者に奉仕するのです。
■「いい組織」「いい会社」の定義
ここ10年で「いい組織」「いい会社」の定義がずいぶん変化してきました。かつては、利益を出して納税する会社が、後に、利益の一部で文化・芸術活動を支援して社会に還元する会社が「いい会社」でした。そしてここ10年では、本業をもって社会問題を解決する会社が「いい会社」とされています。儲けた利益をどこに使うかではなく、儲け方じたいが問われる時代なのです。
だからこそ、人の役に立ちたいという利他の心があり、利他の心から人の役に立つミッション・ビジョンを描き、実現しようとする「サーバントリーダー」は、今の時代の「いい組織」を創るのに重要な役割を果たすのではないでしょうか。

真田 茂人
NPO法人日本サーバント・リーダーシップ協会 理事長
株式会社レアリゼ 代表取締役社長
※部署・役職はインタビュー当時のものです