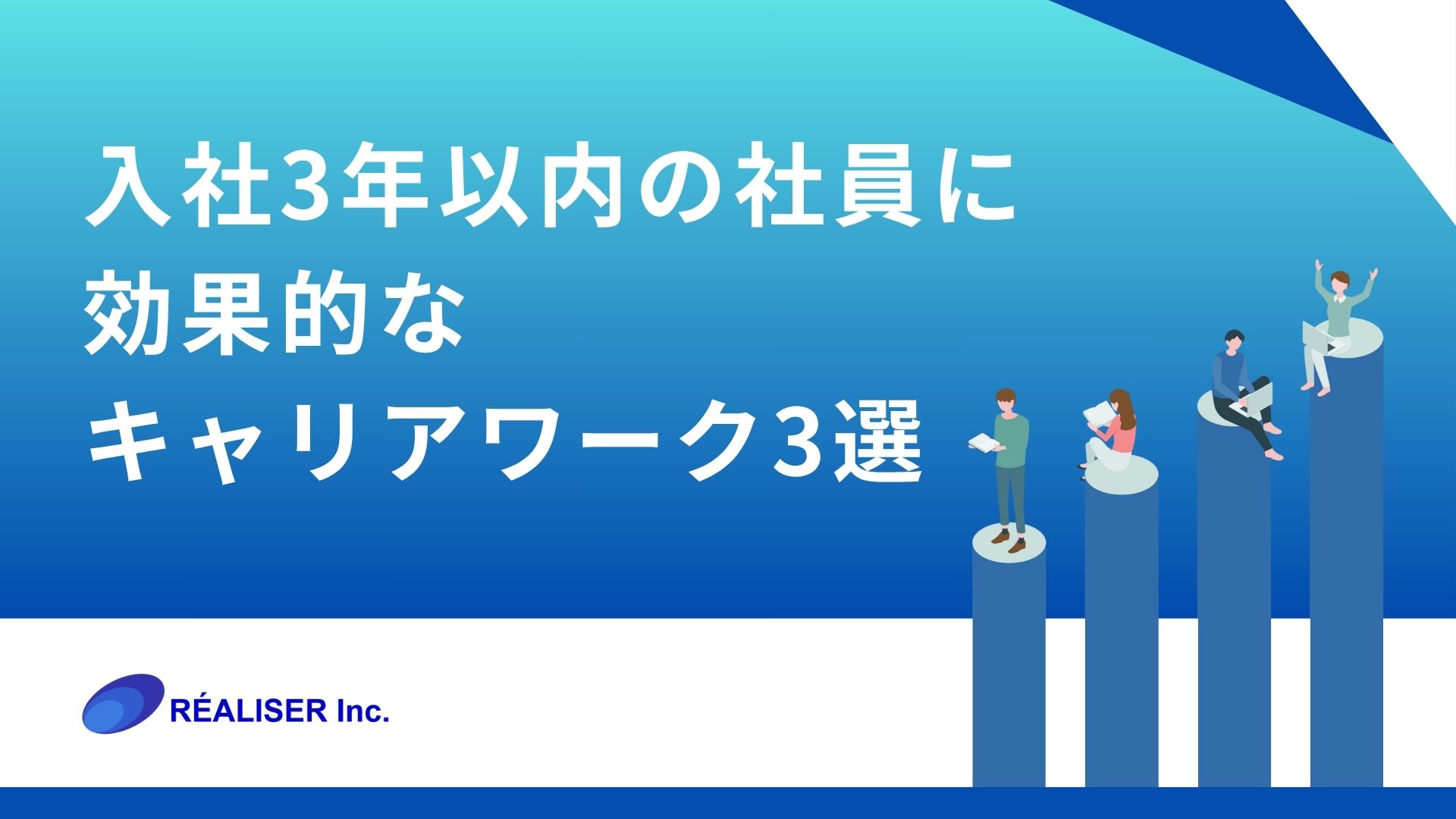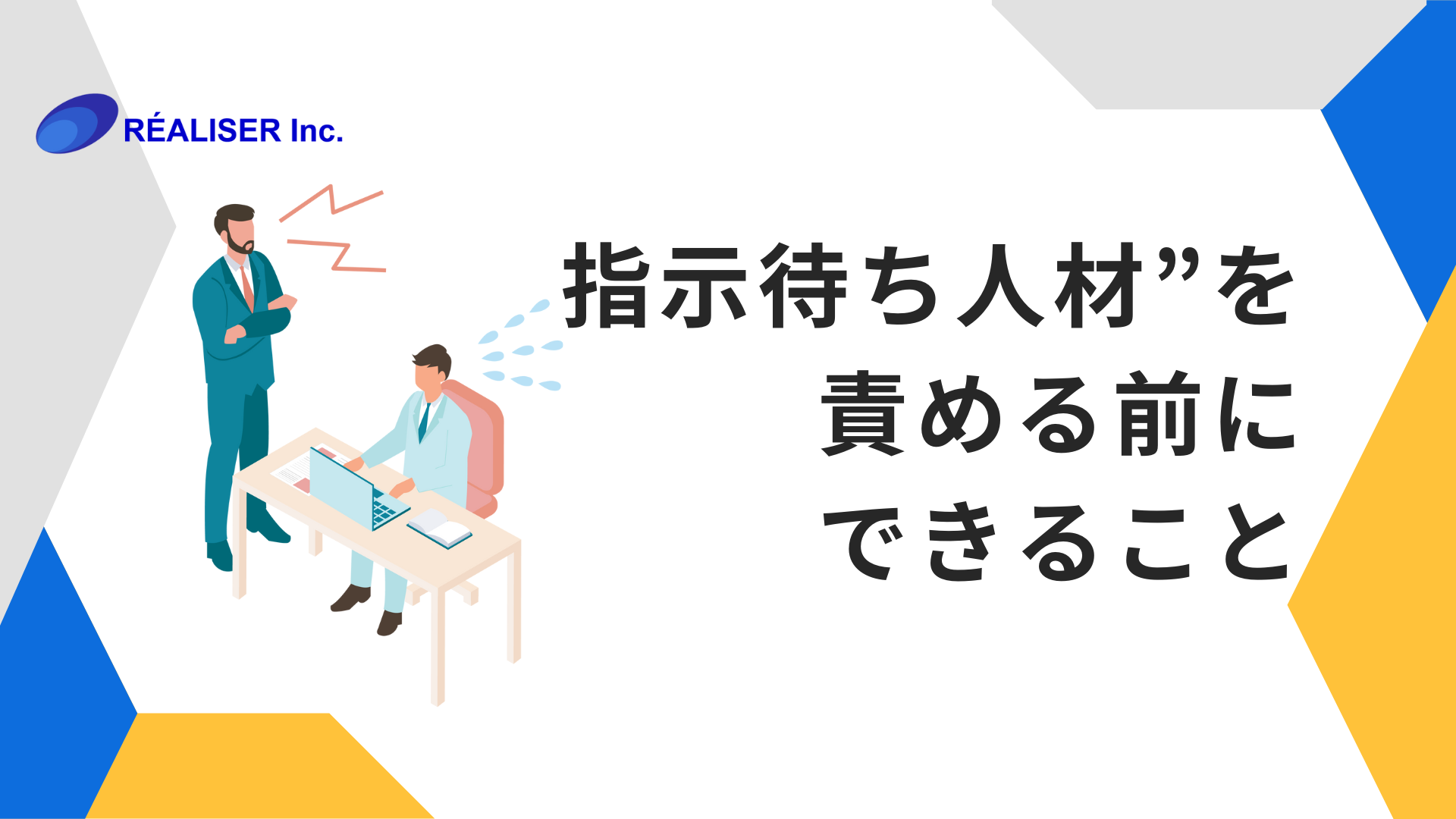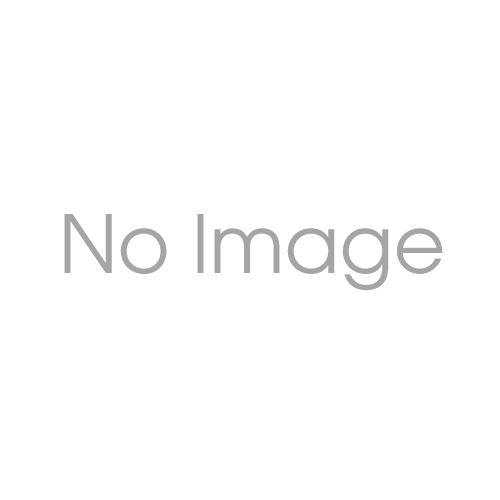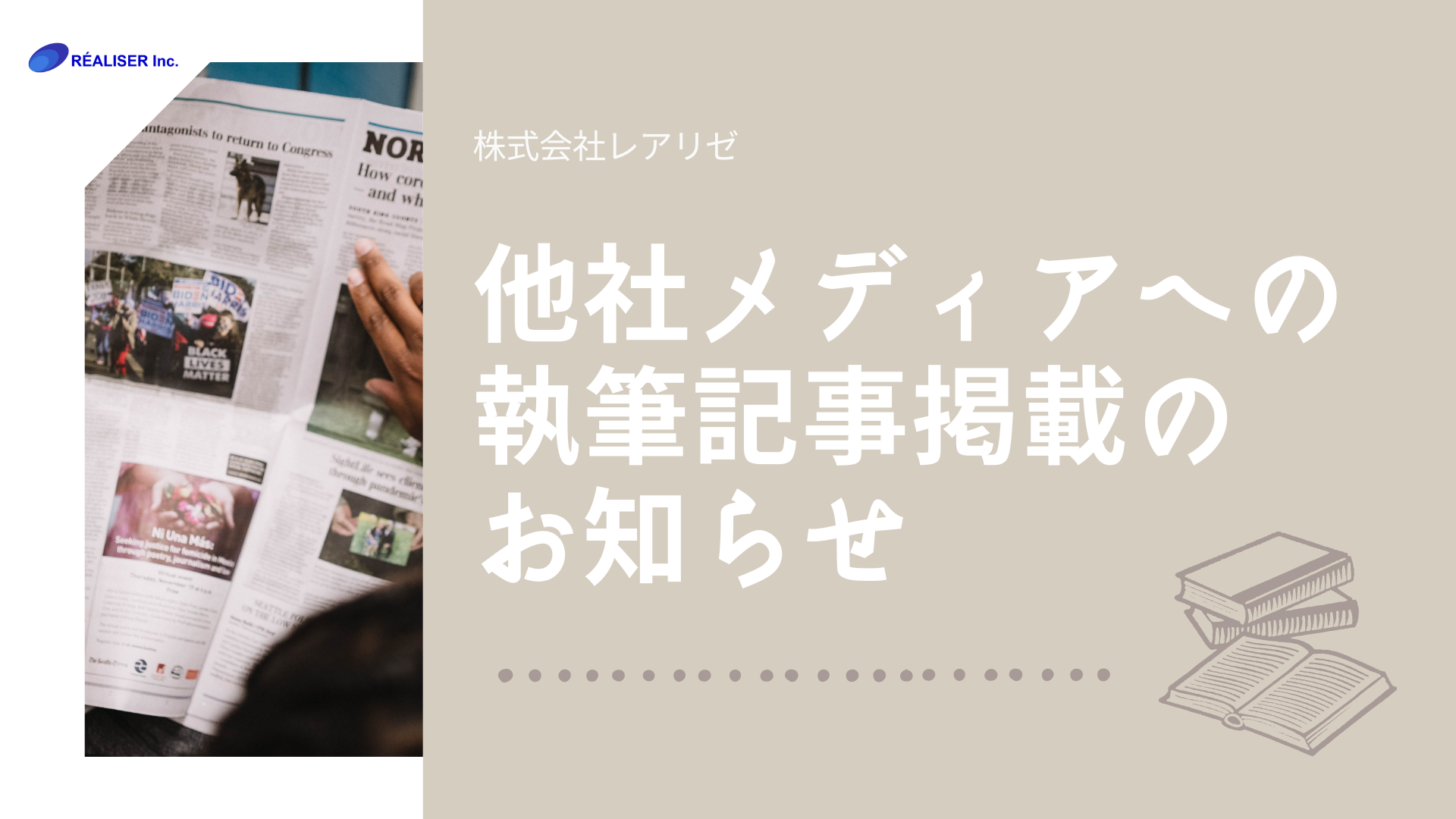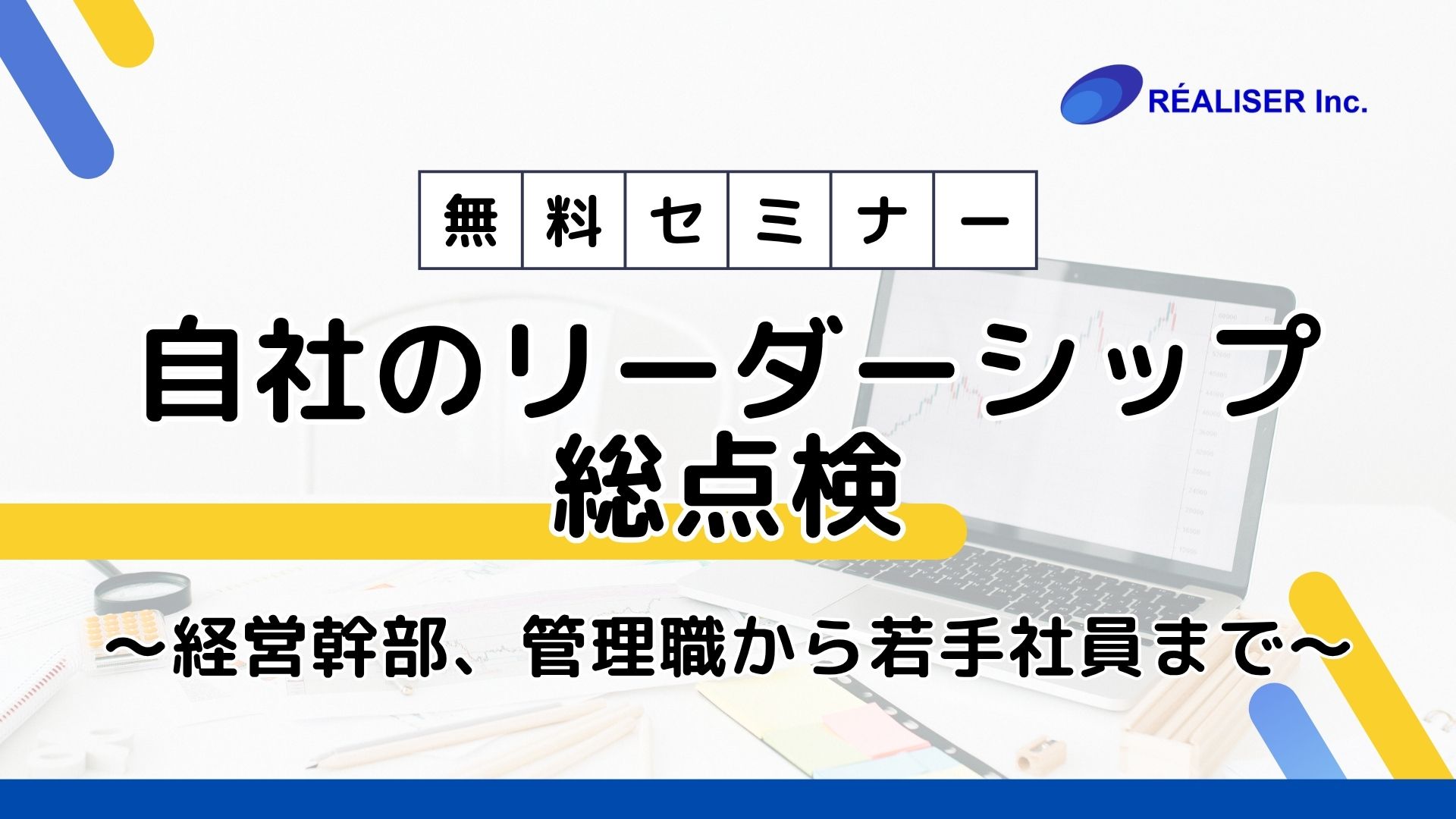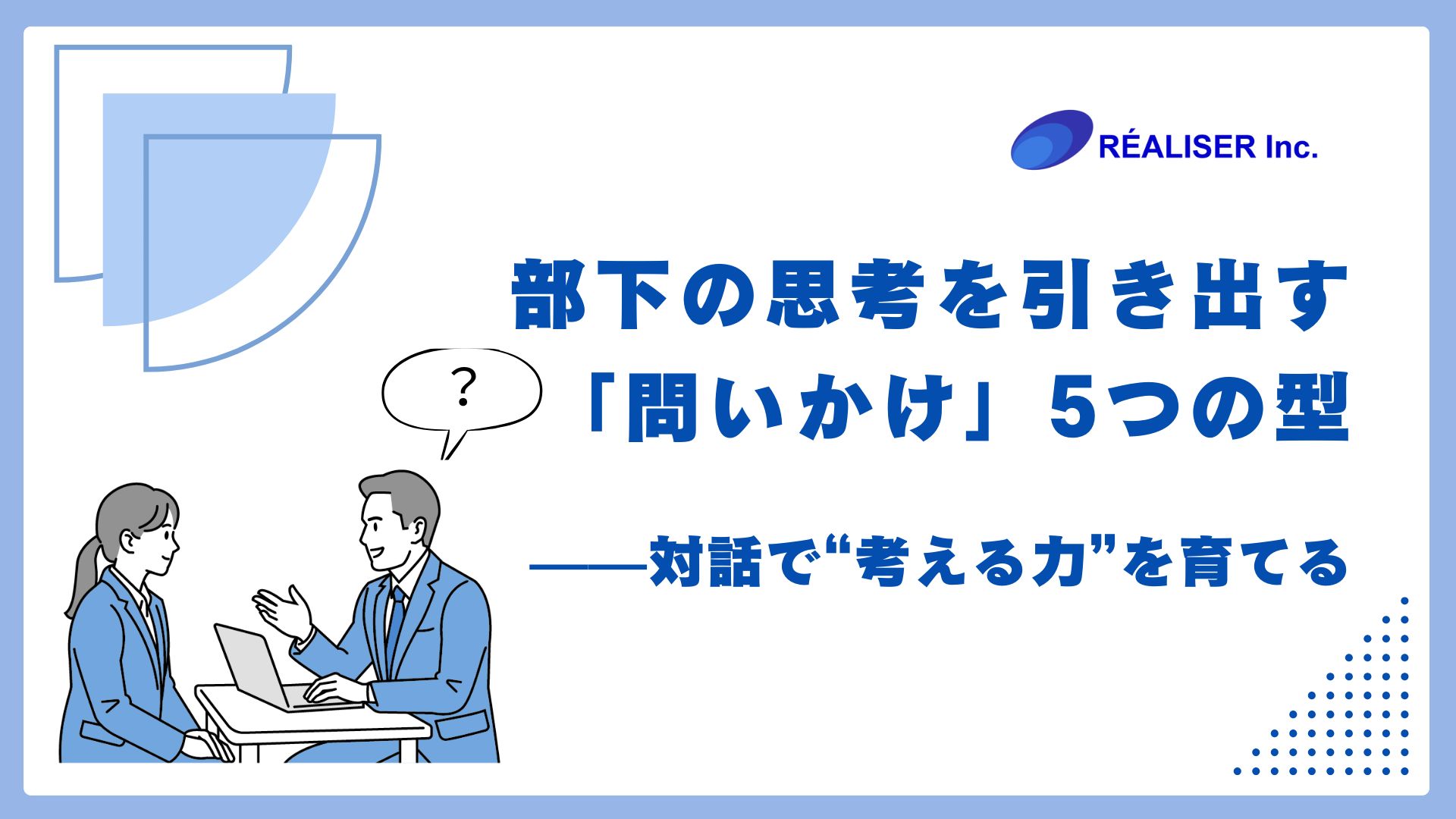
アーカイブ
- 2025年07月 (2)
- 2025年06月 (4)
- 2024年08月 (1)
- 2024年03月 (1)
- 2023年10月 (13)
- 2023年09月 (9)
- 2022年05月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年06月 (1)
- 2021年05月 (1)
- 2020年10月 (2)
- 2020年05月 (5)
カテゴリ
カテゴリ全てを表示タグ
- #テーマ別研修 (38)
- #管理職向け研修 (30)
- #サーバントリーダシップ (25)
- #自律型人材育成 (20)
- #若手社員向け研修 (19)
- #中堅社員向け研修 (18)
- #新入社員向け研修 (16)
- #次世代幹部向け研修 (15)
- #リーダーシップ (14)
- #組織活性化 (13)
- #エンゲージメント (10)
- #コミュニケーション (10)
- #モチベーション・自律 (10)
- #講演レポート (10)
- #経営・組織 (8)
- #執筆者_大川 恒 (6)
- #理念の浸透・再定義 (5)
- #マネジメント (5)
- #メンタルヘルス (5)
- #執筆者_渡邊 義 (5)
- #仕事術・生産性 (4)
- #執筆者_吉田 純一郎 (4)
- #ダイバーシティ (3)
- #心理学 (3)
- #チームビルディング (3)
- #キャリア (3)
- #執筆者_真田 茂人 (3)
- #執筆者_松村 亜里 (3)
- #執筆者_中川 洋二 (2)
- #執筆者_辻 達諭 (2)
- #執筆者_スタンレー・H・グリーン (2)
- #執筆者_石橋 良造 (2)
- #執筆者_青柳 浩明 (2)
- #働き方改革 (1)
- #コミュニティ (1)
- #執筆者一覧 (1)